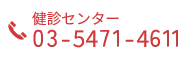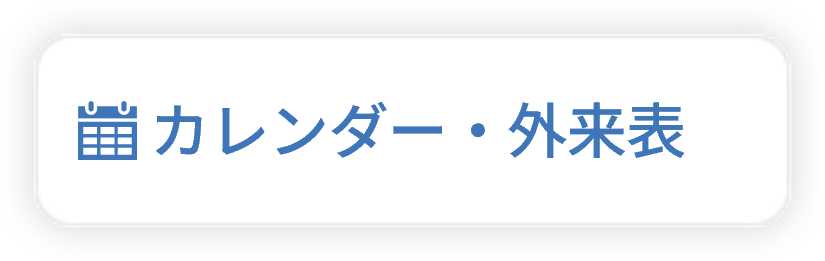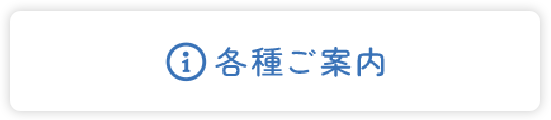いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
糖尿病による三大合併
 糖尿病は、初期ははっきりした症状が現れない傾向にあるため、放置して悪化させ合併症を起こしてからようやく糖尿病にかかっていたことに気づく方もいらっしゃいます。高血糖状態が慢性化すると血管が狭窄し、それにより多くの合併症を招いてしまいます。
糖尿病は、初期ははっきりした症状が現れない傾向にあるため、放置して悪化させ合併症を起こしてからようやく糖尿病にかかっていたことに気づく方もいらっしゃいます。高血糖状態が慢性化すると血管が狭窄し、それにより多くの合併症を招いてしまいます。
特に、以下の部分は細い血管から栄養が運搬されてくるため、糖尿病による障害が起こりやすく、この部分に起こる合併症をまとめて 「三大合併症」と呼ばれます。
糖尿病網膜症
網膜は外側から眼球内に入る光を感知する役割を担っており、糖尿病によって障害され、出血しやすい特徴があります。
糖尿病網膜症は、日本における成人の失明原因で3番目となっています。糖尿病により網膜の血管が障害されて硝子体から出血が起こり、黄斑部がむくみます。そこから悪化すると、硝子体が網膜を引っ張ることで網膜剥離が起きたり、緑内障を起こしたりすることがあり、 失明に至る恐れもあります。
毎年、糖尿病患者の多くが糖尿病網膜症によって失明しています。このような状態にならないためにも糖尿病網膜症を予防することが大切です。糖尿病の患者様は血糖値の上昇しないようにコントロールすることを続け、症状の有無にかかわらず最低でも1年に1回は眼科にて眼底検査を受けましょう。
糖尿病腎症
腎臓は、細い血管である毛細血管が集中しています。腎臓で血液がろ過され、老廃物は尿となって体外へ排出されます。
糖尿病腎症は、高血糖状態が慢性化することで毛細血管が弱くなり、腎機能が低下する疾患です。発症初期は、非常に微量のアルブミン(タンパク質の主成分)が尿中で検出されます。血糖値を上手く管理できていないと進行し、蛋白尿が出るようになります。さらに悪化して腎不全に至ると、腎臓機能を代替するための透析治療が必要となります。
糖尿病は、透析治療を導入する疾患として最多となっています。糖尿病腎症の発症を防ぐために、糖尿病の患者様は血糖値の上昇しないようにコントロールすることを続け、症状の有無にかかわらず定期的に尿検査を受けましょう。
人工透析
人工透析は、ご自宅で実施する「腹膜透析」と医療機関で実施する「血液透析」の2種類に分けられます。
どちらかというと血液透析を実施するケースが多く、腕の血管を流れる血液を外部に出し、透析装置を通して老廃物などを取り除き、不足した物質を補充した血液を再び体内に戻して循環させます。透析治療は1回につき4~5時間かかり、週に3回透析治療に対応できる医療機関に通院することが必要です。
糖尿病神経障害
糖尿病神経障害とは、糖尿病が原因で運動神経や知覚神経、自律神経に障害が及ぶ疾患です。
温度や痛みが分からなくなる、手足が痺れる、内臓機能が低下するなどの症状が現れます。
- 主な症状
- 味覚障害
- 手足の痺れ
- 下痢
- 便秘
- 頻脈あるいは徐脈
- 瞳孔の異常
- 筋力の低下
- 顔面神経麻痺
- 多汗あるいは乏汗
- 勃起不全
- 不整脈
- 立ちくらみ など
上記の症状が示すように、全身に影響を及ぼします。感覚が低下することで、気づかないうちに火傷や怪我をすることが多くなります。
また、糖尿病神経障害は、糖尿病発症から時間が経つほど発症リスクが上昇するため、予防のためには早期から生活習慣を見直すことが重要です。
糖尿病の患者様は血糖値の上昇しないようにコントロールすることを続け、日頃から足の状態をチェックしましょう。
糖尿病の治療
~糖尿病の進行を防ぐために~
POINT!
高血圧などの他の生活習慣病と同じく、糖尿病の予防、進行を抑制するためには食事療法・運動療法が大切です。
食事療法と運動療法だけでは効果が不十分な場合、薬物療法も組み合わせますが、その場合も食事療法と運動療法は続ける必要があります。また、初期から食事療法や運動療法に取り組むことで、合併症の発症予防にも繋がります。
食事療法
食後血糖値を上昇させやすい糖質は
可能な限り減らしましょう
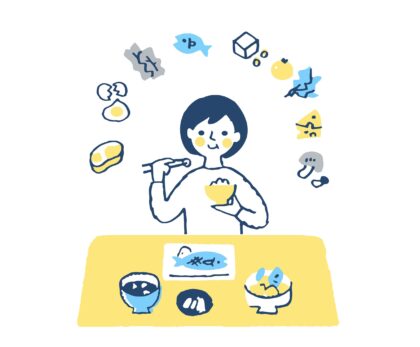 食事では、食事内容や食べ方、過食を控えることを意識してください。脂質、糖質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれていますが、特に血糖値の上昇には糖質が深く関係しています。糖質は、パンやご飯、いも、麺類などに豊富に含まれる栄養素です。
食事では、食事内容や食べ方、過食を控えることを意識してください。脂質、糖質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれていますが、特に血糖値の上昇には糖質が深く関係しています。糖質は、パンやご飯、いも、麺類などに豊富に含まれる栄養素です。
こうしたメニューは可能な限り減らすことを意識してください。
もし、食べたくなったら全粒粉のパン、雑穀米、玄米などで代替するのもお勧めです。
ベジファーストを意識!
早食いは控えよく噛んで食べましょう
血糖値の上昇を防ぐ方法として、食べる順番を意識することが挙げられます。
「べジファースト」と呼ばれる食事方法が有効で、最初に、野菜や海藻類などの食事を先に食べ、糖質を豊富に含む料理は最後に食べます。
糖尿病の患者様は食べ始めてからインスリンの分泌が始まるまでに時間がかかる傾向にあります。野菜→タンパク質(肉や魚など)の順番で食べていき、最後に血糖値の上昇と深く関係する糖質を食べることで、インスリンの分泌が促されます。
また、よく噛むことを意識しましょう。よく噛まずに飲み込んだり、空腹時に糖質を豊富に含んだ清涼飲料水を飲んでしまったりなどの行為は血糖値の上昇を招きます。しっかり噛むことで食事の満足感も得られるので、食べ過ぎも抑えられます。
当院での食事療法
当院の食事療法では、下記のような指導を中心に行っています。
間食・夜食は控えましょう
お菓子は小腹が空いたタイミングで食べることが多いかと思います。
しかし、このタイミングは膵臓が休憩しており、インスリンの分泌が遅れてしまい、血糖値の上昇を招く可能性が高いです。特に、夜食は糖尿病治療にとって悪影響なので控えましょう。
食べる順番を意識し、
よく噛んで食べましょう
上述の通り、食事を食べる順番も大切です。野菜→タンパク質→脂質→タンパク質(糖質)の順に食べるように意識してください。
また、よく噛むことも意識しましょう。
食べ過ぎた日は食後に
適度な運動を行いましょう
糖尿病の治療期間中でも、食べ過ぎてしまう日もあるかと思います。その場合、軽いもので大丈夫なので食後に運動するようにしてください。
血糖値は、食後1時間たってからピークに達します。そのため、食後1時間以内に運動を行うと効果的です。
運動メニューは、ウォーキングや軽めのジョギング、水泳、自転車など、全身を使った適度な有酸素運動が有効です。また、スクワットや腹筋、ダンベルトレーニングなど、筋力に繰り返し負荷がかかる運動も適度な範囲内でするのもお勧めです。
運動療法
運動療法では、
主に以下のような運動を行います。
- 全身を使った有酸素運動:
ウォーキングや軽めのジョギング、
水泳、自転車など
- 筋力に繰り返し負荷がかかる運動:
腕立て伏せや腹筋、
ダンベルトレーニングなど
なお、こうした運動だけでなく、階段の昇降や買い物に行くまでの徒歩での移動、掃除などの軽い運動も有効です。
必要以上に負荷がかかると、意欲の喪失、怪我に繋がる可能性もあります。当院では、患者様の状態や生活習慣、既往歴の有無、スポーツ歴の有無なども踏まえ、適切な運動メニューをお伝えします。お気軽に当院までご相談ください。
食後1時間経過する頃に血糖値がピークとなるので、運動は食後1時間以内に行うのがお勧めです。
食後に取り組みやすい
運動メニューの具体例
血糖値を上昇させないためには運動習慣が大切ですが、無理なく・楽しく続けられる範囲で行うことがポイントです。
無理に負荷が高い運動を行っても中々続かず、また、捻挫などの怪我に繋がる可能性があります。
以下に、食後に取り組みやすい運動メニューの例をまとめました。取り組みやすいものがあれば、是非実践してみてください。
- 食後、10分で大丈夫なので
軽いウォーキングをする - 食べてすぐに洗濯や掃除などの
家事を行う - 食後、あまり動きたくないときは、
ゆっくりストレッチや
柔軟体操をしてみる - 外食の際は、自宅から少し離れている
けれど歩いて行ける距離の店を選ぶ - 外食後は、近隣を少し散歩してみる
- 買い物に行く際は、徒歩もしくは
自転車で行くようにする