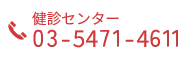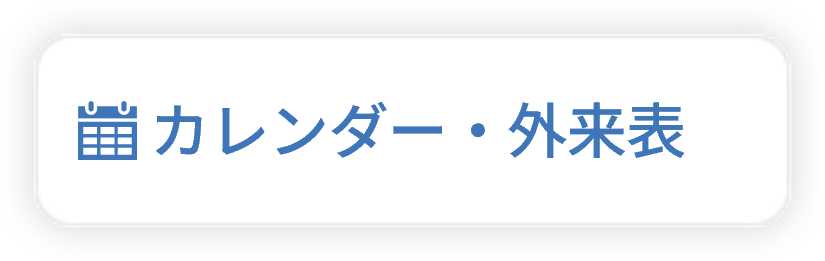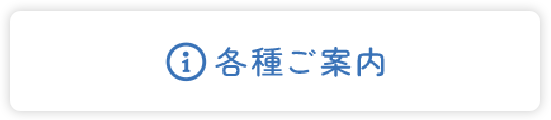いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
肩の動きは
様々な動作に関与しています
 肩に痛みがあると、日常生活における色々な動作に障害が出ます。着替えをする、洗濯物を干す、棚の物に手を伸ばす、通勤時につり革につかまるといった些細なことですら容易にできないなど、普段思い浮かべる以上の多様な場面に肩の動きは関与しています。
肩に痛みがあると、日常生活における色々な動作に障害が出ます。着替えをする、洗濯物を干す、棚の物に手を伸ばす、通勤時につり革につかまるといった些細なことですら容易にできないなど、普段思い浮かべる以上の多様な場面に肩の動きは関与しています。
肩の疾患はスポーツが原因となることも多く、痛みの頻度や程度、どのような動きによって痛みが生じるのかなどを詳細に確認したうえでの正確な診断、適切な治療が必要です。
肩の仕組み
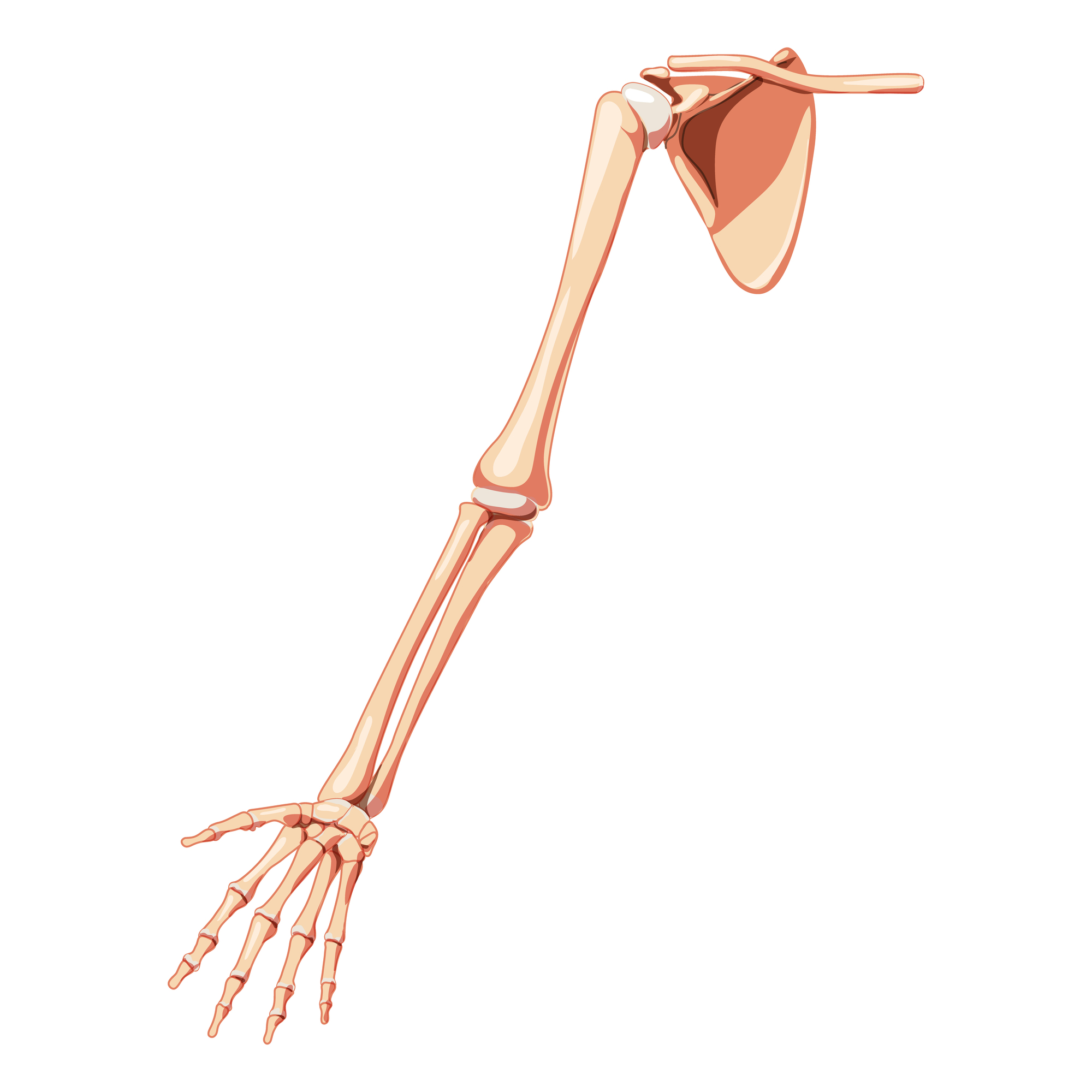 肩関節は、上腕骨の先端が球状に丸くなった上腕骨頭と、その球状の骨頭を受ける関節窩がセットとなって回るように動く関節です。
肩関節は、上腕骨の先端が球状に丸くなった上腕骨頭と、その球状の骨頭を受ける関節窩がセットとなって回るように動く関節です。
関節窩は浅い皿状のくぼみで、背中にある肩甲骨の一部です。くぼみが浅いことで肩の動く範囲は大きくなり、腕を上下左右あらゆる方向に動かすことが可能となります。
上腕骨頭は4つの筋肉によって板状に覆われており、この部分を腱板と呼びます。腕を動かす時には、上腕骨頭は腱板の収縮によって関節窩に近づくので、肩関節が滑らかに動きます。しかし、肩関節部分の骨に変形やズレが生じると肩の動きは制限され、痛みとともに腱板や軟骨部分などにも障害が現れ始めます。肩や腕を動かすことができる可動域も大幅に制限されるため、それまで普通に行っていた日常の動作ができなくなるなど、生活面でも不自由さを感じるようになります。
肩に痛みを起こす原因
POINT!
多様な原因がありますが、怪我に起因する外傷、加齢などの複数の要因によって生じるもの、原因が特定できないものという3つに大別されます。
外傷
主にスポーツや事故などによって生じた肩の怪我、脱臼などがあります。特に転倒時に腕を激しく突いたことで肩に異常を生じるケースが多く見受けられます。
加齢による変性
主に年齢を重ねることで現れるものです。関節周囲の組織に見られる変化で、特に筋肉と骨の付着部である腱板に異常が生じます。
特発性の異常
肩の病気で最も多いものです。一般的に四十肩、五十肩などと言われる症状がこちらに相当します。急に炎症や痛みといった症状を示すものの、大半は原因が明らかではありません。
よくある症状
多くの場合、肩を動かす時に激しい痛みが生じます。
痛みが長期化するにしたがって肩を使う動作を敬遠するようになるので、肩周辺の筋肉の柔軟性も失われ可動域制限が生じ、症状が進行していきます。
肩の痛みの種類
肩こり
肩こりは、長い時間肩に負担がかかり、筋肉に疲労物質が蓄積して硬くなることで血流が低下するために生じると考えられています。
これには、姿勢の悪さ、高さの合わない枕の使用、ストレスなどが関係しています。痛みを引き起こす疲労物質の蓄積を解消するためには、ストレッチを毎日行うなど血行を改善することが重要です。
肩関節の炎症
五十肩などでの痛みは炎症によって生じます。
力こぶを作る上腕二頭筋の腱に炎症が起こり、腱が付着する関節周辺に痛みが現れます。痛みがあるために腕を動かさないことが増えると、肩関節が固くなり動かせる範囲が制限されてしまう場合もあります。自然に回復することもありますが、痛みが強い時には鎮痛剤を用いながら、無理のない範囲で肩や周辺の筋肉をストレッチすることも必要です。
肩関節の損傷
肩関節の動きには、関節の安定性を高める関節唇と呼ばれる軟骨と腱板(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋および腱の総称)が大切な働きをしています。
どちらも繊細なため、過負荷状態が続いて障害が起きると肩周囲の痛みに繋がります。特に、腱に傷が入って切れてしまう腱板断裂(けんばんだんれつ)は、五十肩と似た症状を示します。気になる症状がある場合は、あまり我慢せず、痛みの原因を知り適切に対処するためにも整形外科をご受診ください。
肩の痛みを起こす主な疾患
肩関節周囲炎(五十肩)
五十肩の原因は、肩関節周囲の腱板、関節包の炎症です。 50〜60代の方に多く、癒着性関節包炎または凍結肩と呼ばれることもあります。
突然肩の痛みを感じるようになり、肩を動かす動作による痛みや腕を上げにくいなどの症状が現れるようになります。 症状は徐々に変化し、初期は軽度だったものが安静時にも痛みが起こるようになり、肩の動きに制限が見られるようになっていきます。五十肩の特徴に、片側だけに症状が出やすい点があります。 また、耐え難い症状の1つとして、夜間眠っている時に肩が強く痛む夜間痛が知られています。激しい痛みがある時は安静を心がけ、可能な範囲で肩を動かしながら筋肉のストレッチを行うことが重要です。
頚肩腕症候群(肩こり)
肩こりの原因は、筋肉の疲労です。
筋肉の疲労は、単に筋肉を使い過ぎて生じるのではなく、運動不足、日常の姿勢、ストレスなどの生活習慣によっても起こります。肩を動かす習慣をつけ、筋肉を鍛えることも必要です。 また、運動不足は肥満や生活習慣病へと繋がります。
腱板断裂
腱板断裂とは、肩関節に負担がかかる動作が続いたことにより、腱板に傷が入り切れて痛みが生じる状態です。
加齢が原因となり中高年以降での発症が多いのですが、それ以外にも肩を使う動作が多いスポーツや喫煙習慣が引き金となる場合もあります。肩の動作に伴う痛みだけでなく、安静時や睡眠時の痛みも多く見られます。また、肩関節周囲の筋肉を十分に動かせないため、筋力低下にも気を付けなければなりません。 加齢による腱板断裂の治療では、主に薬物療法、ストレッチ、筋力強化を目的とする理学療法が行われます。
肩峰下インピンジメント症候群
肩峰下インピンジメント症候群とは、腕を上げる動作時に腱板や滑液包(かつえきほう)などが肩の骨に衝突することで痛みが生じ、腕が上がらなくなる状態のことです。
肩峰は、肩関節の一部である肩甲骨にある突起で、インピンジメントとは衝突のことです。腕を上げる、逆に上から下げる動作時に激しい痛みを伴います。原因として、肩関節を構成する筋肉のアンバランスが挙げられる他、スポーツなどによる障害で症状が現れることもあります。
石灰沈着性腱板炎
(石灰性腱炎)
石灰沈着性腱板炎とは、40〜50代の女性に多い肩関節の腱板に生じた炎症による肩の痛み、動かすことでさらに強い痛みが起きる疾患のことです。
突如、夜間に強い痛みを感じて目が覚める、痛みのため肩を動かせなくなるという特徴があります。 石灰沈着性腱板炎は、痛みが現れてから1〜4週に強い症状を示す急性型、1〜6ヶ月中等度の症状が続く亜急性型、6ヶ月以上運動時痛が続く慢性型に分類されます。診断は、腱板の石灰沈着をX線検査で確認することに加え、超音波検査やCTで石灰沈着の大きさや位置を調べることで行います。
肩の痛みに対する主な検査
肩関節を詳しく調べるため
画像検査を行います。
X線検査
肩関節を構成する骨の変形や骨折の確認など形態的な面と、動作時における骨の衝突の程度や負担が生じやすい構造の有無など機能面も詳しく調べることができます。
MRI
肩関節内部の腱板、筋肉、軟骨などの軟部組織の様子を詳しく調べることができます。