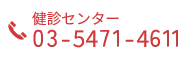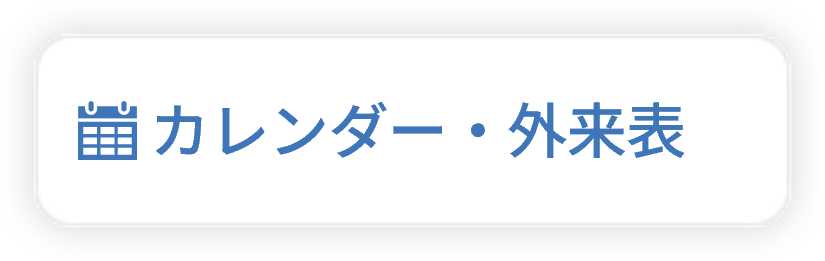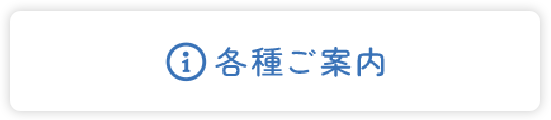いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
骨粗鬆症とは
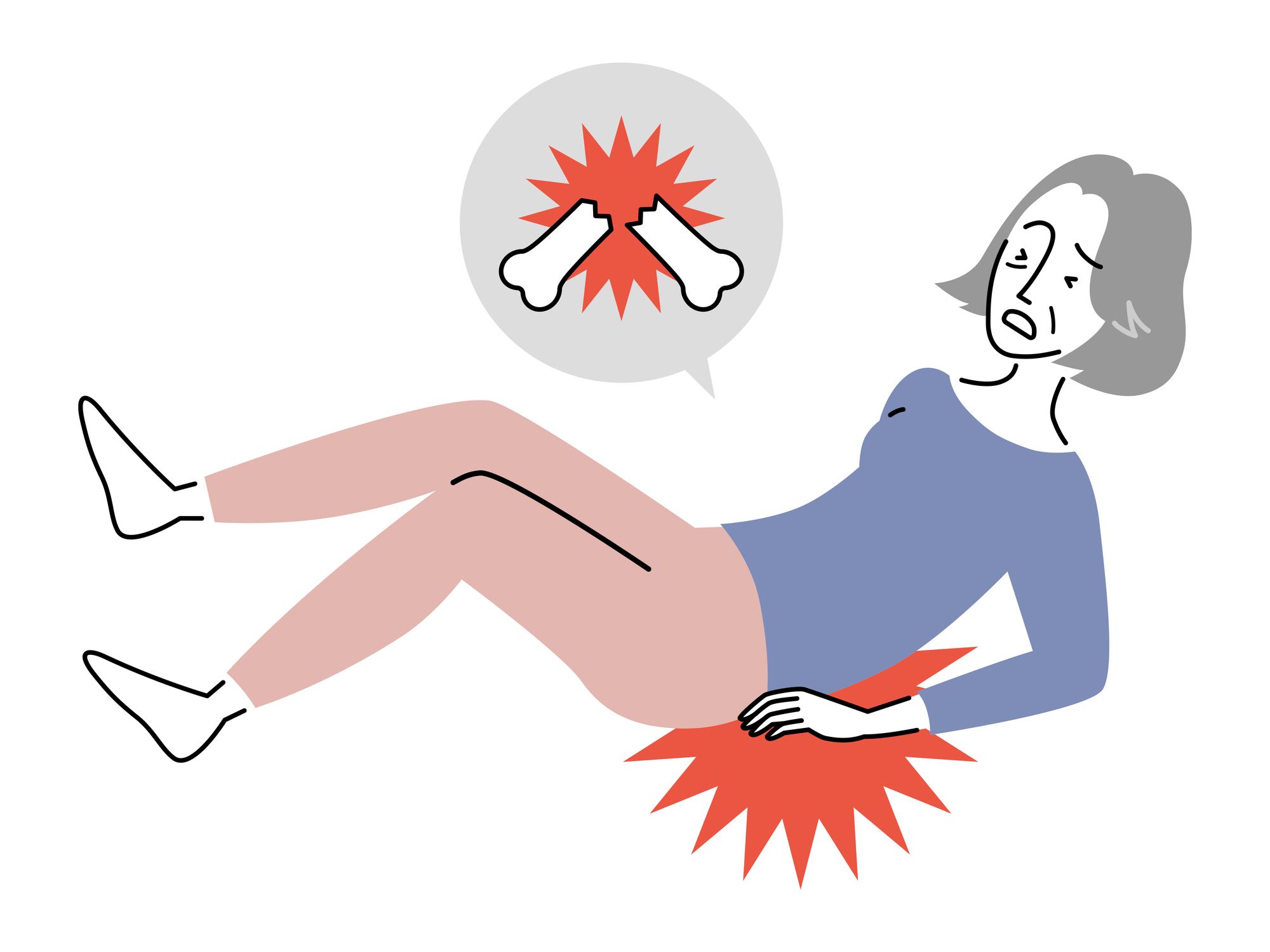 骨粗鬆症とは、骨の密度が低下して骨が弱くなり、骨折が生じやすくなる病気です。
骨粗鬆症とは、骨の密度が低下して骨が弱くなり、骨折が生じやすくなる病気です。
骨の密度が低下すると、くしゃみやつまずいて手や肘をついたなどの些細な力でも骨折してしまう危険性があります。骨粗鬆症が原因の骨折は、要介護状態になる場合もあります。骨粗鬆症は、気付かないうちに進行していることが多いため、定期的に骨密度を調べることが大切です。
当院では、通常の診察で行う検査以外にも、人間ドックや健診の追加項目として骨密度検査をお受け頂けます。
骨粗鬆症による
骨折リスクの高い部位
 骨粗鬆症による骨折を起こしやすい部位は、手首(橈骨)、腕のつけ根(上腕骨)、背骨(脊椎椎体)、脚のつけ根(大腿骨近位部)があります。
骨粗鬆症による骨折を起こしやすい部位は、手首(橈骨)、腕のつけ根(上腕骨)、背骨(脊椎椎体)、脚のつけ根(大腿骨近位部)があります。
圧迫骨折とは、背骨に身体の重みなどがかかることで潰れ、骨折を起こして腰や背中が曲がる病状のことです。圧迫骨折があっても、自覚症状に乏しい場合や腰痛だと思って気付かないケースがあります。1ヶ所だけの骨折でも、骨折周囲の骨に過度な力がかかり他の部位にも骨折が広がることがあるため、早期発見・早期治療が重要です。
大腿骨近位部に起こる骨折の約85%は、転倒によるものです。脚のつけ根を骨折することによって歩けなくなり、介護が必要になるリスクが高まります。骨粗鬆症の治療と並行して、転倒を防ぐ対策も実施しなければなりません。
骨粗鬆症と健康寿命の関連性
日本は、世界的にもよく知られている長寿国の1つです。
最近では、単に寿命だけではなく、健康面での障害がなく、不自由を感じずに日々の生活を送ることのできる健康寿命を延ばすことに関心が向けられています。
日本人の平均寿命と健康寿命を比べると、男性では約9年、女性では約12年の開きがあります。
この結果から、健康とは言い難い期間が長期にわたることが示されています。
骨粗鬆症の予防に取り組み、身体や日々の活動を支える骨をより良い状態に保ち、健康寿命を延ばしていきましょう。
骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の患者様の8割は女性で、特に閉経後に発症する方が多いと見られています。
その理由は、加齢や女性ホルモンの減少による骨密度の低下に加えて、運動不足、喫煙、偏食、お酒の飲み過ぎ、無理なダイエットなどによる栄養不足も関与するためです。近年増えてきた若い世代の骨粗鬆症は、無理なダイエットなどが原因だと言われています。
その他、骨粗鬆症に繋がりやすい疾患として、ステロイドの長期服用、関節リウマチ、糖尿病、慢性腎不全などが挙げられます。
これらの疾患が原因となる骨粗鬆症は、続発性骨粗鬆症と呼ばれます。
エストロゲンと骨粗鬆症
 骨密度には、女性ホルモンの1つであるエストロゲンが深く関与しており、閉経によるホルモン量の変化が骨粗鬆症の発症を高めると考えられています。60代では半数の約5割、70代では約7割が骨粗鬆症だと言われています。
骨密度には、女性ホルモンの1つであるエストロゲンが深く関与しており、閉経によるホルモン量の変化が骨粗鬆症の発症を高めると考えられています。60代では半数の約5割、70代では約7割が骨粗鬆症だと言われています。
50歳を過ぎたら特に自覚症状がなくても、骨密度検査を受けることが推奨されています。骨粗鬆症の早期発見・早期治療のためにも、定期的に検査を受け、健康寿命を延ばしていきましょう。
骨粗鬆症の検査
 問診を行い、症状の有無、具体的な症状、怪我、既往歴などを詳しくお伺いします。
問診を行い、症状の有無、具体的な症状、怪我、既往歴などを詳しくお伺いします。
問診後に骨密度検査、X線検査、血液検査、尿検査を受けて頂き、全ての結果を基に診断を行います。
受診のきっかけが骨折である場合、脆弱性(ぜいじゃくせい)骨折ではないか調べます。脆弱性骨折とは、健康な骨がわずかな力で骨折してしまうことを言います。脆弱性骨折であった場合、骨粗鬆症が考えられるため、さらに詳しい検査を実施して患者様の状態を確認します。
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の治療には、薬物療法、
運動療法、食事療法があります
 当院では、症状の程度、患者様の生活様式、既往歴、合併症、定期薬などから多角的に判断して治療法を選択します。近年、骨粗鬆症の薬物療法は目覚ましい進歩を遂げ、なかでも骨形成促進剤であるテリパラチドなどは、投薬期間は限定されますが、 短期間での骨密度増加の他、新たな骨折抑制効果も期待されています。骨粗鬆症による圧迫骨折で受診された患者様の治療に骨形成促進剤を用いることで、 症状の大幅な改善に繋がったケースもあります。当院では、骨折のリスクが高い骨粗鬆症の患者様には骨形成促進剤をお勧めしています。
当院では、症状の程度、患者様の生活様式、既往歴、合併症、定期薬などから多角的に判断して治療法を選択します。近年、骨粗鬆症の薬物療法は目覚ましい進歩を遂げ、なかでも骨形成促進剤であるテリパラチドなどは、投薬期間は限定されますが、 短期間での骨密度増加の他、新たな骨折抑制効果も期待されています。骨粗鬆症による圧迫骨折で受診された患者様の治療に骨形成促進剤を用いることで、 症状の大幅な改善に繋がったケースもあります。当院では、骨折のリスクが高い骨粗鬆症の患者様には骨形成促進剤をお勧めしています。
なお、症状が軽度~中等度の患者様には、 デノスマブ、ビスフォスフォネート、選択的エストロゲン受容体拮抗剤、ビタミンD製剤を 投与します。運動療法は、患者様の体重を利用して無理なく行います。ウォーキング、 片足立ち、階段昇降なども効果があると言われています。
食事療法は、骨形成に必要なカルシウム、ビタミンD、ビタミンKの摂取が有効です。この時、カルシウムとビタミンDを一緒に摂ることで吸収力が上がます。また、患者様の必要量に応じたタンパク質を摂取することは骨密度の低下防止にも繋がります。