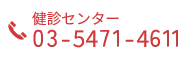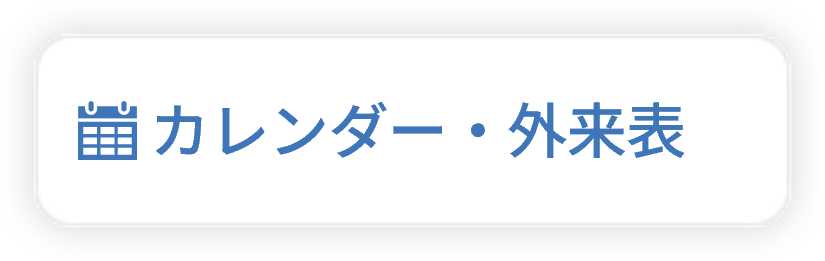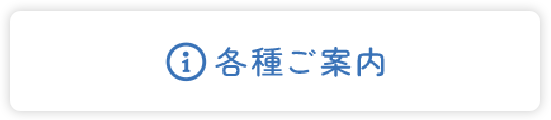いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
心臓の疾患
血管の疾患
動脈疾患
静脈疾患
POINT
心臓の疾患
心筋梗塞
動脈硬化や血栓などが原因となって心臓の血管が閉塞し、心筋が酸欠になって壊死します。また、狭心症が進行して心筋梗塞を発症することがあります。発症すると、突然胸部が痛くなったり息苦しくなったりしますが、そのまま放置すると命に関わります。
狭心症
主に動脈硬化が原因で心臓の血管が細くなり、血流量が低下します。初期にはほぼ自覚症状はありませんが、悪化した場合、胸部の痛み、息苦しさ、動悸などの症状が生じます。 狭心症が進行してさらに危険な心筋梗塞を発症するのを防ぐために、早期発見、早期治療が大切になる病気です。
弁膜症
心臓の弁の機能が低下し、血液の逆流や血流量が低下します。初期にはほぼ自覚症状はありませんが、悪化した場合、胸部の痛み、息苦しさ、動悸、むくみなどの症状が生じ、意識を消失する場合もあります。また、突然死の原因になる場合もあります。
心筋症
遺伝、免疫異常、ウイルス感染などが原因となって心臓の筋肉が異常を起こし、心機能が低下します。原因が特定できない場合もよくあります。心筋症になると、動悸、息切れ、咳、息苦しさ、むくみなどの症状が生じます。悪化すると、意識を消失する場合もあります。また、突然死の原因になる場合もあります。
不整脈
脈が飛ぶ、早くなる(頻脈)、遅くなる(徐脈)など、脈拍が不規則になります。運動や興奮などで一時的に不整脈になる場合もありますが、心不全、冠動脈疾患、弁膜症などの疾患が原因となって、不整脈が起こる場合があります。不整脈になると、動悸、息切れ、胸痛、めまい、ふらつきなどが生じることが増えます。場合によっては、失神することもあります。
心不全
不整脈、心筋症、心筋炎、弁膜症、高血圧など、様々な疾患が原因になって、心臓の機能が低下し、血液を正常に送り出せなくなっています。
血管の疾患
動脈疾患
大動脈瘤
心臓から血液を全身に送り出す大動脈にできた瘤(こぶ)を大動脈瘤と言います。大動脈瘤が破裂すると命に関わるため、緊急手術が必要になります。
大動脈解離
大動脈は、外膜・中膜・内膜の3層から成り立っていますが、大動脈解離になると内膜に裂け目が入り、血液が中膜に流れ込み、中膜が解離した状態になります。大動脈解離の原因は不明ですが、動脈硬化や高血圧が関与しているとされています。 さらに、中膜に入り込んだ血液が偽腔と呼ばれる血液を通す管を作り、血管が外に膨らんで大動脈瘤を形成します。これを解離性大動脈瘤と呼びますが、この大動脈も破裂すると命に関わります。
閉塞性動脈硬化症PAD
動脈硬化が進むにつれ、足の血管が細くなったり詰まったりして、血流が低下します。そのため、歩行時に足が痛んだり、痺れたり、冷たく感じたりする症状が出現します。さらに悪化すると、安静時にもこうした症状が起こります。
静脈疾患
下肢静脈瘤
足の血管にボコボコとした瘤が現れ、これを下肢静脈瘤と呼びます。下肢静脈瘤は良性であり、それ自体が健康に悪影響を及ぼすことはありませんが、外見上の問題や足がむくみやすくなるという問題があります。重症化すると、湿疹、潰瘍、出血に繋がることがあります。
静脈血栓症
足の静脈で血流が悪くなったり、凝固が亢進したりして血栓ができることがあります。血栓が生じると、さらに静脈の血流を停滞させるために下肢の腫脹、疼痛、色調変化が起こります。
肺動脈塞栓症
主に足の静脈で血栓が生じ、分離して血流に乗って体内を移動し、肺に至って動脈を詰まらせます。 肺動脈塞栓症は、胸痛、動悸、息苦しさ、失神などの症状が現れます。肺周辺の太い動脈が詰まった場合、命に関わることもあります。
生活習慣病が及ぼす
循環器への影響
生活習慣病は近年増加傾向にあり、
心臓病の原因になります
 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化を進ませます。
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化を進ませます。
要するに、生活習慣病は、血管や心臓などの循環器に深く関係しています。 実際、生活習慣病の1つである動脈硬化は、狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などを引き起こします。特に狭心症や心筋梗塞は、生活習慣の乱れのために、昨今発症数が増えていっています。
生活習慣病は、多くの場合、自覚症状なく進行するため、それまで健康に問題がなくても、健康診断で数値の異常などが検知された場合には、できる限り早く当院にご相談ください。