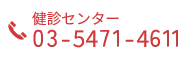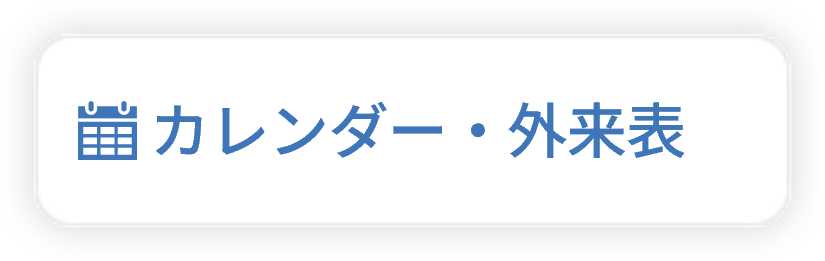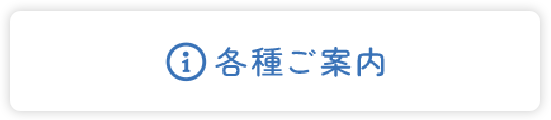いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
片頭痛
片頭痛は年間有病率が8.4%と推定され、特に女性に多い疾患です。
片頭痛は前兆のあるものとないものがあります。前兆としてはキラキラした光やギザギザの光が見えることが多く、通常は前兆から60分以内に片頭痛が始まり4~72時間続きます。片頭痛は、片側の拍動性頭痛を特徴とし、悪心、嘔吐、感覚過敏を伴います。発作時の急性期治療には主にトリプタンが使用されており、軽度の場合は非ステロイド性抗炎症薬やアセトアミノフェンが使用されますが、急性期治療薬を使用しすぎると偏頭痛が悪化したり慢性化したりすることがあるため、注意が必要です。なお、頭痛がない日もお薬を飲んで、頭痛発作を起こりにくくしたり、頭痛発作が起きても軽くすむようにするための予防療法を行うことがあります。
片頭痛の新しい治療薬を取り扱っています
エムガルティ(在宅自己注射)
エムガルティは2021年4月末に承認された片頭痛の予防薬(発症抑制薬)です。
月に1回の注射で済むため、毎日服用する薬とは異なり、通院は月1回のみです。反復性片頭痛や慢性片頭痛で従来の予防薬が効果を示さず、日常生活に支障をきたしている方(1ヶ月に4日以上の頭痛発作がある方)に適しています。注射部位の痛み以外の重大な副作用は報告されていません。
アジョビ(在宅自己注射)
アジョビは2021年6月に承認された片頭痛の予防薬(発症抑制薬)です。
片頭痛は、「CGRP」という物質が脳の血管に作用することで発生するとされています。アジョビはこのCGRPに結合し、その働きを抑えることで片頭痛の発作を減らす効果が期待できます。注射薬であり、4週間ごとに1回1本、もしくは12週間ごとに1回3本の注射を行います。後者の場合、1回で3本分の費用がかかりますが、通院回数を減らすことができ、患者の負担を軽減できます。
アイモビーク(在宅自己注射)
アイモビークは2021年6月に承認された、国内初の抗CGRP受容体モノクローナル抗体による片頭痛予防薬です。
CGRP受容体に結合してその働きを抑え、片頭痛の発作を防ぐ効果があります。初回は70mg(1本)を皮下注射し、その後は4週間ごとに1本のペースで継続します。主な副作用として、便秘、注射部位の赤み・かゆみ・腫れ・疼痛、傾眠などが報告されています。
レイボー
レイボーは2022年1月に承認された、急性期の片頭痛治療薬です。
片頭痛発作時にのみ使用し、予防的な使用は避けてください。片頭痛が始まったら早めに服用することが推奨されます。通常の用量は1回100mgですが、効果や頭痛の状態に応じて調整可能です。服用後、痛みが和らいでも再度痛みが戻った場合、追加で服用することができますが、24時間以内に200mgを超えないようにしてください。また、追加服用による副作用の増加は認められていません。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は、反復性(月に15日未満)と慢性(月に15日以上、4ヶ月以上)に分類され、それぞれ圧痛の有無でさらに細分化されます。
頭痛は圧迫感や締めつけ感のある非拍動性の頭痛で、通常は両側に発生します。痛みのレベルは軽度から中等度で、日常生活に支障が出ることはありますが、寝込むほどではありません。こうした頭痛が30分から、長い時は7日間継続します。原因は、口や顎の機能異常、精神的ストレス、筋性ストレス、薬剤乱用などがあります。発作性緊張型頭痛の治療にはNSAIDsが使用されますが、筋弛緩作用を持つ抗不安薬との併用がより効果的な場合があります。
慢性緊張型頭痛には、予防療法として抗不安薬や抗うつ剤を毎日一定量服用することがあります。
パーキンソン病
パーキンソン病は、中脳にあるドパミン神経細胞の脱落で発症します。
症状は静止時振戦、筋固縮、無動/寡動、姿勢反射障害の4徴候が特徴ですが、診断には無動/寡動が必須で、静止時振戦と筋固縮のいずれかまたは両方が必要とされます。より正確な診断には、ドパミン補充療法の効果や嗅覚障害などの支持基準が必要で、さらに診断精度向上にはMIBG心筋シンチとダットスキャンが有効です。
治療は年齢により異なり、若年ではジスキネジアを避けるためレボドパを避けますが、高齢ではレボドパを初めから使用します。他の治療薬として、MAO-B阻害剤、COMT阻害剤、抗コリン剤、ドパミン作動薬、アデノシンA2a受容体拮抗剤、ゾニサミドがあります。薬剤以外の治療法として、デュオドーパや脳深部刺激療法があります。
てんかん
てんかんは、てんかん発作を起こす脳疾患で、年齢や性別に関係なく発症し、原因により「特発性てんかん」と「症候性てんかん」に分類されます。
てんかん発作を繰り返すのが特徴で、生涯で一度でも発作を経験する人の割合は約10%と考えられていますが、発作を何度も繰り返して「てんかん」と診断される人の割合は約1%と考えられています。発作時の症状は、発症年齢や脳の病変部位により異なります。小児てんかんは、通常は継続的な治療が必要ですが、成長に伴って改善することもあります。
特発性てんかん
検査をしても原因が分からないてんかんです。てんかん自体に遺伝性はないとされていますが、発作を起こしやすい体質は遺伝する可能性があると言われています。多くのてんかん患者様は、このタイプに該当すると考えられています。
症候性てんかん
脳外傷、脳梗塞、脳炎、髄膜炎など、脳に起きた損傷や障害が原因でおこるてんかんです。
重症筋無力症
重症筋無力症は、午前中は軽い症状ですが、午後になると悪化する日内変動と、疲れやすく症状が悪化する易疲労性が特徴です。調子がいいと症状が見られないこともあり、診断が遅れる場合があります。診断には、アセチルコリン受容体抗体やマスク抗体を検出する血液検査、筋電図、胸部CTやMRIなどが用いられます。ただし、約15%の患者様は抗体が検出されず、診断が難しくなります。
治療は可能で、胸腺腫がある場合は手術で切除します。胸腺腫がない場合、全身型では抗コリンエステラーゼ阻害薬と少量のステロイド、免疫抑制薬を併用します。この処方で反応が悪い場合は、血漿交換、免疫グロブリン、ステロイドパルス療法などが実施されます。
脳梗塞
脳梗塞になって脳の血管が詰まると手足の動きや感覚が麻痺し、言葉が話せなくなるなどの症状が現れ、進行すると意識を失うこともあります。
脳梗塞は、高齢者に多く、発症機序からアテローム血栓性脳梗塞と心原性脳塞栓症の2種類に分類できます。前者は高血圧や糖尿病、脂質異常症がリスク要因であり、後者は心房細動が原因で、心臓が規則的に脈を打てなくなります。症状が出てから早い時期に、tPA療法によって血栓を溶解させたり、カテーテルを詰まった血管のなかに通して再開通させたりすることで後遺症を減らすことができます。tPA療法は発症から4.5時間以内、血栓回収療法は数時間以内が対象です。
痺れ
痺れは実際に発症している症状を表す言葉です。したがって、痺れが起きる根本的な原因として、脳や脊髄など中枢神経系の障害や、もしくは全身に分布する末梢神経系の障害が潜んでいることもあります。
具体的な原因は多岐にわたり、神経内科の病気である脳卒中でも痺れが生じますが、内科や外科の病気のために痺れが起こることもあります。例えば、内科領域では糖尿病、整形外科領域では椎間板ヘルニアや変形性脊椎症です。このように痺れの原因は多く、重い病気の可能性もあるため、痺れが起きた場合は早急に神経内科を受診してください。