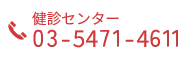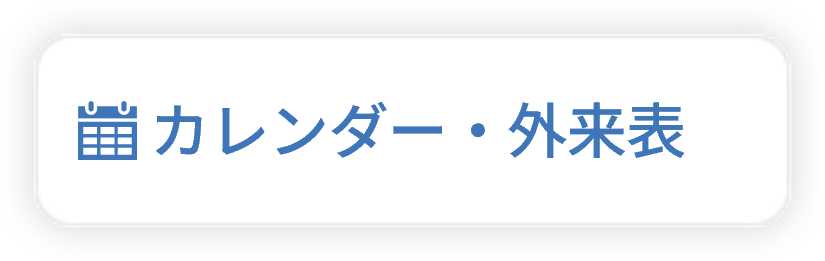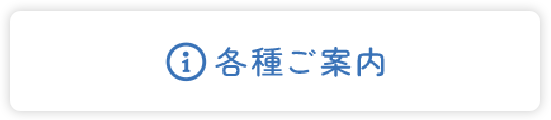いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
次のような症状はありませんか?

- 胸部の違和感
- 息切れ
- 脈が飛ぶ
- 動悸
- 一時的な意識の消失
- めまい
上記のような症状があれば、
不整脈が疑われます。
健康診断で不整脈(心電図異常)
と指摘された場合
 心臓は筋肉からなる臓器であり、筋肉の収縮によってポンプのように体に血液を送り出しています。具体的な仕組みとしては、心臓の筋肉に電気信号が伝わり、その刺激で順次筋肉が収縮し、心臓が血液を送り出すようになっています。
心臓は筋肉からなる臓器であり、筋肉の収縮によってポンプのように体に血液を送り出しています。具体的な仕組みとしては、心臓の筋肉に電気信号が伝わり、その刺激で順次筋肉が収縮し、心臓が血液を送り出すようになっています。
通常、心臓は必要に応じて速度を変えながら、1分間に60~100回規則正しく拍動しています。不整脈は、心臓に伝わる電気信号に異常が生じ、脈が速すぎたり(頻脈)、遅すぎたり(徐脈)、あるいは不規則になったりして、正常な脈拍が保たれないことを言います。 不整脈は、健康な人でも起きやすいものから、深刻な病気が隠れている危険なものまで様々です。
健康診断などで心電図の異常や不整脈が指摘された場合、最初に不整脈の種類を正しく把握することが重要です。
不整脈の3つの種類
POINT!
不整脈は原因や症状によって詳細に分類されていますが、心拍の状況から分類すると、3種類に分類されています。
1.頻脈性不整脈
頻脈性不整脈では、心拍数が1分間に100回以上にもなります。電気刺激の発生が異常に速かったり、電気の通路に短縮ルートができて回路を形成し、そこに電気が通ったり、空回りしたりするなどで起こります。 頻脈性不整脈には、心房細動、心房粗動、心室頻拍、心室細動、発作性上室頻拍、WPW症候群などがありますが、なかでも、致死性不整脈である心室頻拍や心室細動はリスクが高いので、ご注意ください。
2.徐脈性不整脈
徐脈性不整脈では、心拍数が1分間に50回以下になります。 心拍数が減るため、脳や臓器へ送られる血液が減り、息切れ、めまい(目の前が急に暗くなる症状、めまいの一種である眼前暗黒感も含む)、意識消失と言う症状が起きます。 徐脈は高齢者や動脈硬化が進行している方に多いとされています。徐脈が直ちに命を左右することは多くないため、深刻な自覚症状がない限りしばらく様子を見ることになります。
3.期外収縮
期外収縮が起きると、心拍が飛んだり、心拍が乱れたりします。健康な状態でも、過労や喫煙などで生じることがあり、不整脈の中でも一番多い症状です。期外収縮の種類として、心房性期外収縮(上室性期外収縮とも呼ばれる)や心室性期外収縮がありますが、それぞれ心房細動や心室細動を引き起こすことがありますので、特に心疾患をお持ちの方はご注意ください。
危険な不整脈「心房細動」
心房細動は、それ自体は死に直結しませんが、リスクの大きい不整脈の1つです。
この不整脈は、心臓の上半分を占める心房から非常に高頻度に電気信号が放出され、脈の速度が一定にならなくなり、不整脈を起こします。 血液は体内で心臓を通じて血管の中をいつも流れていて止まることがないので、心臓や血管の中で血液が固まってしまうことはありませんが、心房細動になると、心房は震えた状態となり血液のよどみができて血の塊ができやすくなります。その血の塊が心臓から外に出て、例えば脳に流れて脳血管が詰まると、脳梗塞を発症することがあります。
また、心房細動が続くと、脈が異常に速いため心臓の筋肉が疲れてしまい、ポンプとしての機能が低下することがあります。 心房細動が起きても自覚症状はないこともありますし、息切れや動悸が起こることもあります。また、長期間心房細動が続いて、慢性になってしまうこともありますし、一過的に発生する場合もあります。後者を発作性心房細動と呼びます。
不整脈の原因
 不整脈は、心筋症、心筋梗塞、狭心症などの疾患、甲状腺ホルモンや自律神経の異常などが原因となって発生する場合があります。あるいは、服用中のお薬の副作用が原因となって、不整脈が発生する場合もあります。
不整脈は、心筋症、心筋梗塞、狭心症などの疾患、甲状腺ホルモンや自律神経の異常などが原因となって発生する場合があります。あるいは、服用中のお薬の副作用が原因となって、不整脈が発生する場合もあります。
また、喫煙、アルコールの過剰摂取、ストレス、睡眠時無呼吸、生活習慣病などの日常生活での要因が相まって不整脈が起きる場合があります。
しかし、原因が明確でない不整脈も多いです。先天的または後天的に、心臓で異常な電気活動が発生することで不整脈が起きると言われています。
不整脈の検査
心電図検査
最も基本的な検査です。心臓が出す電気信号の波形を検出し、分析します。なお、不整脈が検査時に起きないと不整脈を検知することができないので、次の24時間ホルター心電図検査が勧められます。
24時間ホルター心電図検査
小型の心電計を装着して、帰宅後も含め24時間、心電図検査を行います。院内での短時間での心電図検査では検出できない狭心症の有無や不整脈の頻度などを調べることができます。
心超音波検査
超音波を照射して、心臓の大きさや心筋の厚さなどの形態、心筋の収縮、弁の動き、筋肉の動きなどの心機能を調べます。 不整脈は、心疾患を発症しておりその結果として起きる場合もありますし、不整脈の他に異常が起きていない場合もあります。そのため、この検査によってもともと心疾患があるかどうかを診断します。
不整脈の治療方法
不整脈の治療が必要だと診断された場合、最初に飲み薬で治療が行われます。薬剤としては、主に不整脈が起こりにくくなるお薬や、脈拍が安定するお薬を服用します。心房細動などで血の塊が生じやすい不整脈の場合、血液を固める凝固因子の作用を抑制する抗凝固薬を服用することもあります。
飲み薬で症状が改善されない場合、さらなる治療として、カテーテルを用いて血管内から心臓にアクセスし、心臓の中の異常な電気回路の原因となっている部分を焼灼または冷凍凝固するカテーテルアブレーションを行ったり、脈が遅すぎる場合にはペースメーカーを埋め込んだりする治療法に進むこともあります。
ペースメーカーによる治療が
検討される症状
- だるさや息切れなどの症状を強く示し、
日常生活に影響が出ている - 脈が遅くなって意識が消失し、
事故や大怪我を起こすリスクがある - 心不全の可能性がある