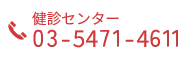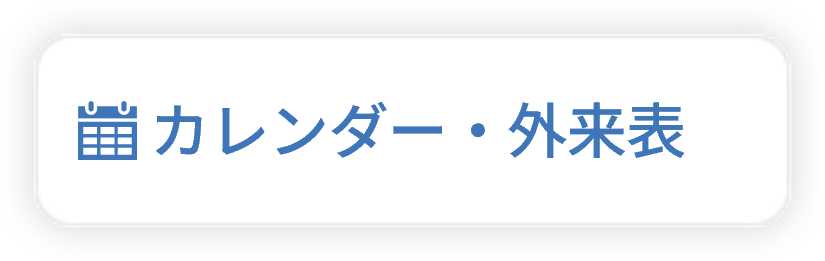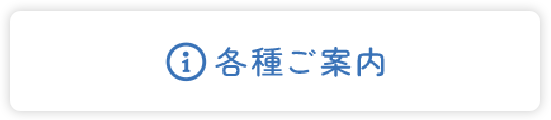いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
食道の疾患
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することにより、食道に炎症を起こす病気です。
食道がん
食道がんとは、食道上皮細胞ががん化したものです。主な原因は、長年にわたる飲酒・喫煙習慣です。初期には症状がほとんど見られません。症状としては胸の違和感、つかえる感じ、体重減少、胸背部の痛みなどが出現します。そのため、内視鏡検査による早期発見、早期治療が重要です。
食道バレット上皮(バレット食道)
食道バレット上皮とは、逆流性食道炎などにより、食道粘膜は強酸性の胃酸に曝露されて炎症が生じ、食道上皮が胃粘膜に置き換わる疾患です。食道がんに繋がる可能性があり、定期的に検査を受けて状態を観察することが必要です。
好酸球性食道炎
白血球の1つである好酸球が食道壁に慢性的な炎症を発生させる疾患です。主な症状として、のどのつかえ感、飲み込みづらさなどが起こります。治療は、胃酸を抑える薬や内服タイプのステロイド剤を使用した薬物療法が行われます。
食道カンジダ症、カンジダ性食道炎
カンジダはカビ(真菌)の一種で、皮膚や粘膜に存在しています。疲労の蓄積、風邪をひいた、などの免疫力が落ちているような状態の時に増殖して感染することがあります。ときに無症状のことも多いですが、ときに、のどの違和感、飲み込み時の痛み、胸部の不快感、吐き気・嘔吐などの症状を示すことがあります。通常は免疫力の回復に伴って症状も治まります。治療が必要な場合は抗真菌薬を内服します。
食道アカラシア
食道と胃の間には下部食道括約筋という筋肉があります、食道アカラシアは、この筋肉の弛緩がうまくいかなくなり、食道蠕動運動の低下も伴って、食べ物が胃に届かずに食道に停滞してしまう疾患です。食後に胸痛や嘔吐などの症状が現れ、就寝中にも嘔吐が起こります。また、食べ物が気管に入り、誤嚥性肺炎になることもあります。
胃の疾患
急性胃炎
胃に起こる急性の炎症で、ストレスや過度な飲酒、アレルギー、内服薬の副作用、ウイルスなどが原因となります。放置していて自然に治ることもありますが、強い炎症が起きている場合は薬物療法を実施します。
胃びらん(びらん性胃炎)
炎症により胃粘膜がただれた状態です。多くの場合は無症状ですが、症状が出ている場合には薬物療法を実施します。
慢性胃炎
胃粘膜に発生した炎症が慢性化している状態です。無症状のことも多いですが、みぞおちの不快感、胸やけ、胃もたれ、胃痛などの症状が起こることもあります。 ピロリ菌感染が原因になることが多く、感染が判明した場合は薬剤による除菌治療を行う必要があります。
萎縮性胃炎
慢性胃炎が10~20年と長期間に及んだ場合、胃粘膜が萎縮する萎縮性胃炎が起こります。主な原因は、ピロリ菌感染です。胃がんに繋がる可能性が高いため、除菌治療が必要です。また、除菌後も胃がんの発症有無を確認するために、年に1回の内視鏡検査が推奨されます。
胃潰瘍
胃粘膜に発生した炎症により、胃壁の深くまでダメージが及んだ状態です。症状は、上腹部やみぞおちの痛み、胃もたれ、吐き気、出血を伴う場合には黒色便(タール便)、貧血などがおこります。ピロリ菌感染が原因であることが多く、他にもストレス、解熱鎮痛剤・抗血栓薬等お薬の内服などが挙げられます。薬物療法を実施し、ピロリ菌感染のある場合は除菌治療を行います。
胃がん
胃粘膜の細胞ががん化したものです。従来から日本人の発症例が多かったのですが、近年はピロリ菌の除菌治療を受ける方が増えてきた背景もあり、胃がんの発症数は以前より減少傾向にあります。しかしながら、がん全体でみるといまだ発症数は多い現状にあります。初期には症状がほとんどありません。また症状としては胃炎や胃潰瘍と同様です。胃がんの検査は内視鏡検査で行います。早期発見・早期治療により完治が期待できますので、定期的に検査を受けましょう。
胃ポリープ
主なポリープに胃底腺ポリープ、過形成性ポリープがあります。
機能性ディスペプシア
食道や胃に器質的異常は見つからないものの、みぞおちの痛み、みぞおちの焼けるような感じ、食後の胃もたれ、食事を開始してすぐ起こる膨満感が繰り返し続く疾患です。ストレスの解消、食事や生活習慣の改善が必要です。様々な種類の薬物療法が行われます。
アニサキス症
アニサキスは寄生虫の一種で、サバなどの魚介類に寄生しています。アニサキスが寄生した魚をしっかり加熱しない状態で食べることにより、アニサキスが胃や腸の粘膜を傷つけることで炎症が起こり、腹痛や嘔吐などの症状を示します。胃アニサキスでは内視鏡でアニサキスを見つけ出し、取り除くことで症状は治まります。
十二指腸の疾患
十二指腸炎
十二指腸粘膜に炎症が発生している状態で、無症状のこともありますが、症状が起きている場合は薬物療法を実施します。ピロリ菌が原因になることもあり、その場合は除菌治療が必要です。
十二指腸潰瘍
十二指腸の壁深くまで損傷が及んでいる状態です。特に夜間、早朝などの空腹時に上腹部痛がおこり、食事をとることで軽快することが多くみられます。ピロリ菌感染が原因になることが多く、その場合は除菌治療が必要です。他にも、過剰なストレス、解熱鎮痛剤や抗血栓薬の服用などが挙げられます。十二指腸の粘膜は胃粘膜よりも薄いため、増悪すると粘膜に穴があく穿孔という状態になりやすいため、早い段階で内視鏡検査を受けていただき治療を開始することが大切です。
大腸の疾患
感染性腸炎・急性胃腸炎
ロタウイルスやノロウイルスなどのウイルス、カンピロバクター、病原性大腸菌(O157)、サルモネラ菌などの細菌への感染で起こる胃腸炎です。ウイルス性の場合、整腸剤の内服治療を行い、細菌性の場合は抗菌薬投与を行います。水分をしっかり摂取できない方は脱水につながる恐れもあり、点滴治療を行いますので、速やかに受診してください。
急性虫垂炎
大腸の起始部にある虫垂に炎症が発生している状態で、俗にいう「盲腸」です。右下腹部に痛みが生じますが、初期は胃の不快感、痛み、吐き気がみられます。治療は抗生物質を用いた薬物療法と手術があり、炎症の程度に応じて適切な治療法を選択します。診断には血液検査、超音波検査、CT検査を用います。
大腸ポリープ
大腸粘膜にできた隆起物です。大腸粘膜にできる隆起物で、ほとんどが腫瘍性のものです。
大腸がん
近年は食生活が欧米化しており、日本における大腸がんの発症数は増え続けています。しかし、前がん病変であるポリープを小さな段階で発見し、切除できれば大腸がんを予防することが可能です。そのため、大腸内視鏡検査を受けることが大切です。40歳を迎えるとポリープができやすくなるので、大腸内視鏡検査を受けましょう。
大腸憩室
大腸内の圧力が上昇することで、大腸壁に窪み(憩室)が生じた状態です。憩室に出血や炎症が起こる場合があり、血便や腹痛が起きた場合、大腸憩室症が原因の1つとして疑われます。
大腸憩室出血
憩室粘膜は、正常な大腸粘膜よりも薄く脆いため出血する可能性があり、それに伴って血便が排泄されます。腹痛は伴わないことが多いです。抗血栓薬を服用している方はリスクが高くなります。出血量が少ない場合は、食事を控えて安静にすることで自然に止まりますが、大量出血となったり何度も起きたりする場合は、入院治療や内視鏡による止血処理などが必要になります。
大腸憩室炎
大腸憩室に細菌が感染して炎症が起こると大腸憩室炎となります。腹痛・発熱などの症状が起こります。抗菌薬を使用することで症状が治まることが多いですが、炎症が激しくなった場合、憩室に穴が開くこと(穿孔)がありますので、早期に検査・治療を受けましょう。
虚血性腸炎
大腸の血管が一時的に詰まってしまい血流が低下することで、大腸粘膜が虚血状態になり、炎症が発生する疾患です。糖尿病や高血圧に伴う動脈硬硬化など血管の要因と便秘など腸の要因が複合して発病すると考えられています。症状は、最初に下腹部やわき腹の痛みが起こり、次第に血が混入した下痢が出るようになります。炎症を鎮めるには、食事を控え、安静にすることが必要で、入院治療が必要になることもあります。
潰瘍性大腸炎
直腸から連続的に大腸粘膜に炎症が起こり、腹痛や下痢、血便などの症状が生じる疾患です。現在のところはっきりとした原因は分かっておらず、難病指定を受けており、発症数も増加し続けています。症状が起こる活動期(再燃期)と症状が治まる寛解期を交互に繰り返すため、医師の指示に従ってお薬の内服を続け、できる限り寛解期を長くすることが大切です。大腸内視鏡により確定診断を行います。
クローン病
潰瘍性大腸炎と同じく明らかな原因が不明で、難病指定を受けており、同様の症状が起こりますが、炎症や潰瘍形成が口から肛門までの消化管全域に起こります。 クローン病は特定の食品で悪化を招く恐れがあり、食事制限・栄養療法を行うことが多いく、このように潰瘍性大腸炎とは別の疾患なので治療法が異なります。寛解期も専門医による適切な治療を継続することで、落ち着いた状態をキープする必要があります。
過敏性腸症候群
器質的異常がないにもかかわらず、腹痛に伴って下痢や便秘が繰り返し起こる疾患です。「下痢型」「便秘型」「混合型」の3つのタイプに分けられます。知覚過敏や腸の蠕動運動に異常が起こることで発症するとされており、薬物療法や生活習慣の見直しにより治療を行います。近年は発症数が増えており、誰にでも起こり得る疾患として捉えられています。
便秘
便秘は本来排泄されるべき便が十分量かつ快適に排出できない状態で、強くいきまないと排泄できない、少ししか出ない、排便後にすっきりしない、3日以上便ができていない、排便前に強い腹痛が起こる、お腹の張りがつらい、などの症状がみられます。浣腸や内服薬なしでは排便できないなどの状態も該当します。
加齢、水分や食物繊維不足、運動不足などで蠕動運動が低下している場合が多いですが、腸疾患などの器質的異常によって起こる場合もあります。
当院では、重篤な疾患が隠れていないか、内服している薬の影響はないかなどを確認し、適切なお薬を用いた薬物療法を行います。
腸閉塞/イレウス
腫瘍などによって腸管が閉塞したり、蠕動運動の障害によって内容物が肛門側に流れなくなる病気です。腹痛や膨満感、嘔吐、便秘などが生じます。
痔
痔は裂肛(切れ痔)、痔核(いぼ痔)、痔ろうに大別されます。治療は主に、軟膏を用いた治療と排便状態の改善指導を実施します。
鼠径ヘルニア
鼠径部(足の付け根)の筋膜が弱まり、腸などの臓器の一部が外に飛び出してしまう病気です。突出した腸などの臓器が周囲の筋肉に締め付けられて元に戻らない状態は「嵌頓状態」と呼ばれ、早急な外科手術が必要になります。
肝臓、胆嚢、膵臓の病気
脂肪肝
肝臓に脂肪が蓄積されている状態です。肥満、飲酒、糖尿病などで生じます。放置すると、肝硬変、肝臓がんを発症することがあります。
胆石疝痛、胆のう炎
胆石が胆のうの出口に詰まると右上腹部や背部に激しい痛みが生じます。胆汁が滞留・逆流することで細菌感染が生じ、胆のう壁に炎症が発生すると胆のう炎が起こります。
急性膵炎
膵液に含まれる消化酵素により、膵臓自体が消化され、膵臓やその付近に突然炎症が起こる疾患です。原因は、おもにアルコールや胆石などが考えられますが、明らかな原因が不明な場合もあります。上腹部痛、背部痛などの激しい症状を示し、命を脅かす重篤な状態になる場合もあります。血液、尿の検査やCT検査などを行い診断します。
膵がん
膵がんの多くは膵管から発生するがんです。要因としては糖尿病や肥満、アルコール、喫煙などがあげられます。家族性にみられることもあります。初期は症状が出にくいことが多いため早期に発見することが難しい疾患です。転移しやすく、進行すると腹痛、体重減少、黄疸、背部痛などの症状が出現します。初めて糖尿病と診断されたり、糖尿病の方で急にコントロールが悪くなった場合にも膵がんを疑って精査をする必要があります。