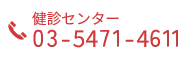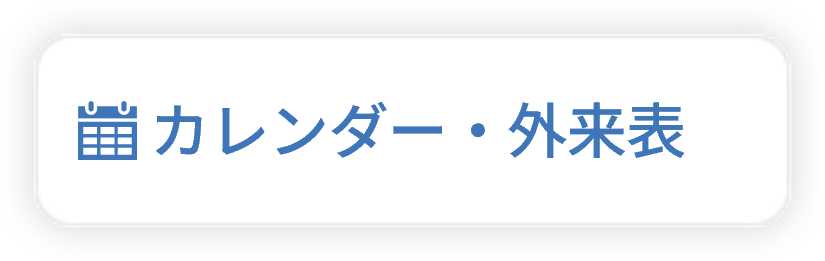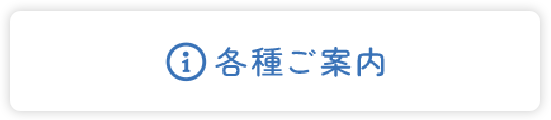いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
高血圧について
 血圧とは、心臓から流れてくる血液が血管を押す力のことを言います。心臓が絶えず伸び縮みしてポンプの役割を果たすことで、血液が全身に行き届きます。血圧は上下しており、心臓が拡張した際に最も低くなり、収縮した際に最も高くなります。血圧計には2つの数字が表示されますが、これを拡張期血圧、収縮期血圧と言います。
血圧とは、心臓から流れてくる血液が血管を押す力のことを言います。心臓が絶えず伸び縮みしてポンプの役割を果たすことで、血液が全身に行き届きます。血圧は上下しており、心臓が拡張した際に最も低くなり、収縮した際に最も高くなります。血圧計には2つの数字が表示されますが、これを拡張期血圧、収縮期血圧と言います。
高血圧とは、血圧が基準値以上に高い状態が慢性化したものです。
血圧は食事や運動、緊張などにより大きく変動するので、測定を1回しただけでは高血圧と診断できず、少なくとも2回以上測定する必要があります。
血圧が高いということは、全身に血液を送る心臓の大きな力が必要となるため、負担がかかっている状態だと分かります。また、高血圧になると血管壁に大きな圧力がかかるため、血管が硬くなり、動脈硬化の進行を招きます。
動脈硬化の進行に伴って血圧も上がる傾向にあるため、高血圧と動脈硬化には相関関係があります。動脈硬化が進行すると障害や疾患が全身に起こるリスクがあるため、注意が必要です。特に、脳卒中や心筋梗塞、腎不全といった重篤な疾患を発症する可能性が高まるため、適切な治療を早い段階から始め、血圧を適正値になるよう管理することが重要です。
女性は、高血圧の発症率が全年齢で減少していっていますが、男性では50代以上はゆるやかに上昇していることが分かっています。
健診の結果などから高血圧と判明した場合、可能な限り早めに当院までご相談ください。
高血圧の原因
POINT!
高血圧は、本態性高血圧と二次性高血圧の2種類があります。
本態性高血圧とは、高血圧の原因が不明なもので、遺伝的要因に生活習慣が影響して発症するのではないかと言われています。高血圧の約9割はこのタイプです。
一方、二次性高血圧は原因疾患がはっきりしており、疾患の症状として高血圧になっているタイプです。特に、血圧を高めるホルモン分泌異常や腎疾患が原因になっていることがよくあり、原因疾患を治療することで血圧も適正値に戻ることが期待できます。
本態性高血圧の
きっかけとなる生活習慣
- 肥満
- 運動不足
- 果物や野菜
(カリウムなどのミネラル)不足 - アルコール摂取過多
- 塩分の摂取過多
- 喫煙
- 精神的ストレス
- 自律神経の失調
二次性高血圧の原因となる疾患
原発性アルドステロン
腎臓の上に位置する副腎から、アルドステロン(血圧を上昇させるホルモン)が過剰に分泌されることで、高血圧が引き起こされる病気です。通常、血圧が高くなると、腎臓から分泌されるレニン(血圧の調整をするホルモン)が低下しますが、原発性アルドステロン症ではアルドステロンの分泌が過剰なため、レニンの分泌量が相対的に少なくなり、高血圧の原因に繋がります。
腎血管性高血圧
何かしらの病気によって腎動脈が狭窄・閉塞し、血流低下が起こり、レニン(血圧の調整をするホルモン)が多く分泌されることで血圧 上昇が起こります。自覚症状が出ない場合が多く見られます。
睡眠時無呼吸症候群
本来、睡眠時は副交感神経が優位となります。しかし、睡眠時に呼吸が浅くなったり、停止したりすることで、睡眠が一時的に中断し、交感神経が働くことによって血圧が上昇します。この繰り返しによって血圧変動が起こり、高血圧に繋がります。また、血圧変動が頻繁に起こることで、心臓に大きな負担をかけてしまい心疾患へのリスクも高くなります。
薬剤誘発性高血圧
薬剤が原因により血圧が上昇することで起こります。複数の医療機関を受診されている方は、新しい薬が始まった後から血圧が高くなることもあります。この場合は、薬剤による高血圧の可能性があります。薬の内服を開始や追加、変更によって血圧の上昇がみられた場合は 薬剤誘発性高血圧を疑います。
血圧が高いことにより起こる
症状と合併症
POINT!
 血圧が基準値より高い状態が続いたとしても自覚症状が乏しいケースが多いですが、病状が悪化すると、息切れや動機、手足のむくみなどの症状が生じることがあります。こうした症状が現れるようになると、高血圧による合併症リスクが高まっている恐れがあります。
血圧が基準値より高い状態が続いたとしても自覚症状が乏しいケースが多いですが、病状が悪化すると、息切れや動機、手足のむくみなどの症状が生じることがあります。こうした症状が現れるようになると、高血圧による合併症リスクが高まっている恐れがあります。
無症状だからといって高血圧に対する治療を受けないでいると、動脈硬化などの進行を招き、心筋梗塞や脳卒中、腎不全などの発症リスクが高まります。
そのため、健康診断や血圧測定を定期的に受診し、異常を指摘された場合は専門の医療機関で治療を受けましょう。
動脈硬化
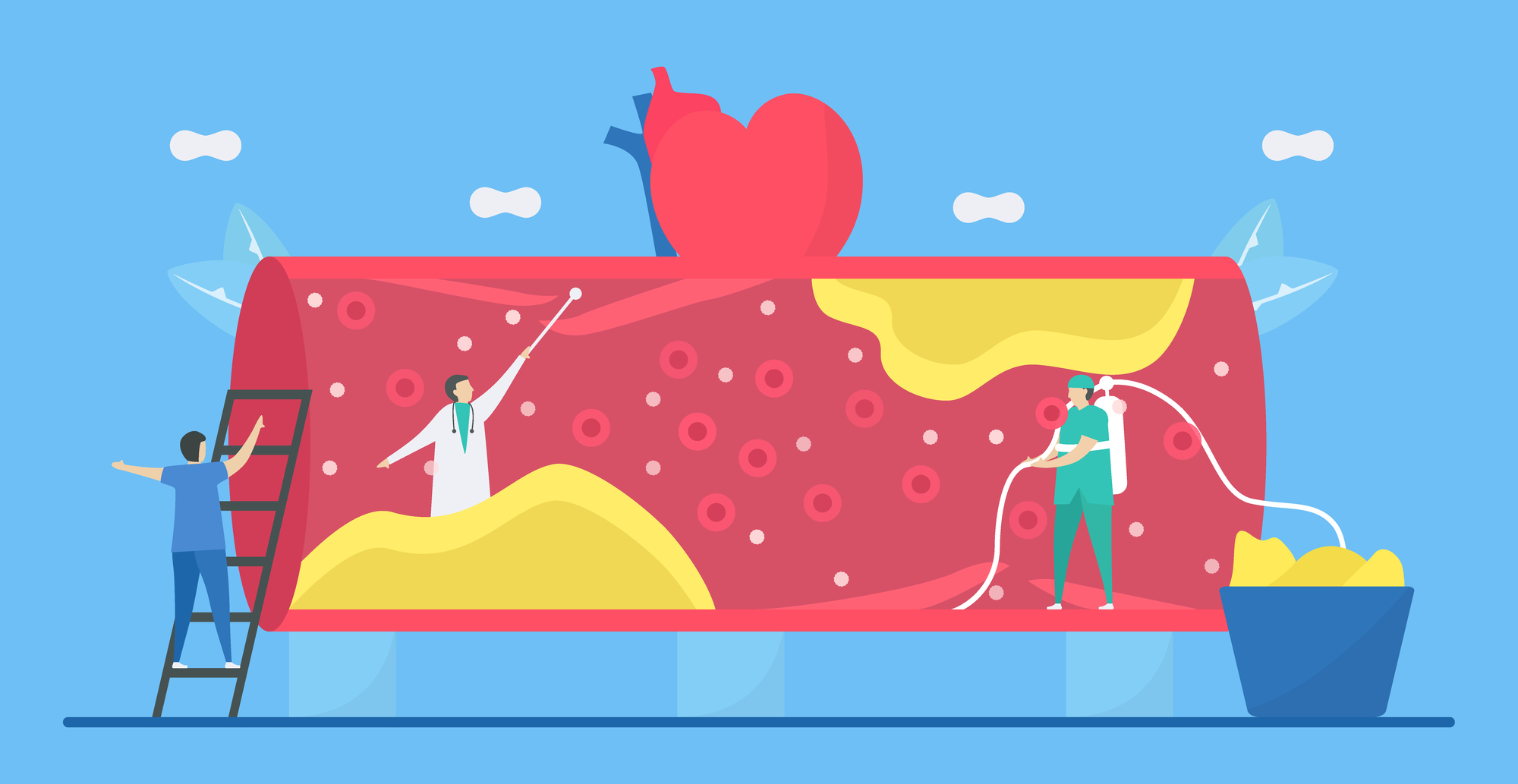 血管壁は通常弾力性を持ち合わせていますが、高血圧状態が続くと動脈硬化を招き、血管の弾力性が少しずつ失われていきます。それにより、血管がさらに強く押されるようになります。このように、高血圧と動脈硬化はお互いに影響し合い、どんどん悪化していきます。
血管壁は通常弾力性を持ち合わせていますが、高血圧状態が続くと動脈硬化を招き、血管の弾力性が少しずつ失われていきます。それにより、血管がさらに強く押されるようになります。このように、高血圧と動脈硬化はお互いに影響し合い、どんどん悪化していきます。
動脈硬化は全身の血管に影響を及ぼし、心肥大や心不全、狭心症や心筋梗塞、脳出血や脳梗塞、腎硬化症や腎不全、大動脈瘤、大動脈剥離、眼底出血などに至る恐れがあります。そのため、血圧と動脈硬化のコントロールが大切です。定期的に健康診断を受け、生活習慣の改善、適切な治療を受けましょう。
頸動脈エコー検査
頸動脈エコー検査は、超音波を使用して頸動脈(大動脈から頭部へ血液を送る血管)に到達し、その反射波を基に動脈硬化の状態を評価する検査です。 検査では、エコーゼリーを首に塗り、こぶしほどの大きさのプローブという医療機器を使って首をなぞりながら行います。プローブを通じてモニターに頸動脈の映像が表示され、その映像を確認しながら動脈硬化の程度を測定します。
エコーゼリーは少し冷たいですが、それ以外に不快感はなく、ベッドに仰向けになっているだけで、体に負担がかかることはありません。
心臓に起こる合併症
血圧が高い状態が続くと、全身に血液を送り出す心臓に過度に負担がかかり、心肥大が起こります。
この状態が悪化した場合、心不全に至る恐れがあります。また、動脈硬化により心臓に栄養素や酸素を届ける冠動脈が狭くなると、狭心症や心筋梗塞に繋がることがあります。
脳に起こる合併症
動脈硬化が進行し、脳の血管が狭くなって詰まったり、破裂したりして脳の機能が失われた状態が脳卒中です。
脳卒中は、くも膜下出血や脳出血、一過性脳虚血発作、脳梗塞に分類されます。一過性脳虚血発作は、脳梗塞と同様の症状が短時間のみ現れ、消失する病態です。脳梗塞のリスクが高い危険な発作です。
腎臓に起こる合併症
動脈硬化は、血液をろ過して老廃物を尿として排出する腎臓に影響し、腎硬化症や腎不全のリスクを高めます。
重症化した場合、人工透析を受けなければなりません。
目に起こる合併症
動脈硬化が進行すると、網膜を走る毛細血管に障害を起こし、高血圧性網膜症や眼底出血を引き起こす可能性があります。
重症化すると、大幅な視力低下、最悪の場合は失明に至ることがあります。
血管に起こる合併症
動脈硬化の進行によって、大動脈瘤や大動脈瘤破裂、大動脈解離などといった重大な血管障害を引き起こすことがあります。
また、足の血管で動脈硬化が進むと下肢閉塞性動脈硬化症が起きることがあり、初期症状として足に痺れや冷えが生じます。こうした症状が現れた場合、早めに受診しましょう。
高血圧の診断基準
日本高血圧学会による
高血圧診断基準
| 分類 | 診察血圧 | 家庭血圧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |
| 正常血圧 | <120 | <80 | <115 | <75 |
| 正常高値血圧 | 120-129 | <80 | 115-124 | <75 |
| 高血圧症 | 130-139 | 80-89 | 125-134 | 75-84 |
| I度高血圧症 | 140-159 | 90-99 | 135-144 | 85-89 |
| II度高血圧症 | 160-179 | 100-109 | 145-159 | 90-99 |
| III度高血圧症 | ≥180 | ≥110 | ≥160 | ≥100 |
| (孤立性)収縮期高血圧 | ≥140 | <90 | ≥135 | <85 |
診察室血圧と家庭血圧
(自己血圧測定)について
血圧は、病院で測定する「診察室血圧」とご自宅で測定する「家庭血圧」に分けられます。家庭血圧では、家庭用血圧計や24時間携帯型自動血圧計(ABPM)を使用します。
血圧は身体活動やストレスなど様々な影響を受け、常に変動しています。そのため、測定場所によって数値が異なることもあります。診察室血圧も家庭血も正しい数値ではありますが、診察室血圧の方が緊張から高値を示すことが多いです。このため、診察室血圧と家庭血圧の数字に乖離があった場合、家庭血圧を参考にします。
白衣高血圧
病院で測定した場合、ご自宅で測定した時に比べ血圧が高く出たことはないでしょうか。
医師や看護師などが着用する白衣に緊張して一時的に血圧が高くなる現象を、「白衣高血圧」と呼び、「診察室高血圧」とも呼ばれます。一時的に高血圧になっているだけなので問題ないと考える方もいますが、持続的な高血圧になる可能性もあるため、普段から血圧が上がらないように気を付けましょう。
高血圧の治療法
まずはお薬を使用しない、運動や食事、
生活習慣の改善を行います。
これらを行っても改善効果が乏しい場合、
薬物療法を組み合わせて治療を行います。
非薬物療法
高血圧が軽度の場合、お薬を使用しなくても血圧を適正値の範囲内に管理できる可能性があります。また、薬物療法を併用する場合も、運動や食事、生活習慣の改善が必要です。治療は長期間に及ぶため、ストレスがかからない範囲で取り組める方法を見つけることが大切です。
生活習慣の改善
ストレスを溜めず、睡眠や休息時間をしっかり取ることが大切です。また、身体が冷えることで血圧の上昇を招くため、冷やさないようにしましょう。
ストレス
ストレスが溜まると血圧の上昇を招きます。スポーツや趣味など息抜きの時間を確保するなど、スケジュールを見直してみましょう。
休息・睡眠
睡眠や休息時間が不十分だとストレスや疲労が溜まり、血圧の上昇を招きます。忙しい時期もあるかと思いますが、できるだけ睡眠や休憩時間を取るように心がけましょう。
血行の改善
冷えは血圧の上昇を招くため、身体を冷やさないように気を付けましょう。湯船につかると血管が拡張して血行が良くなるので、夏の時期でもできる限り湯船につかるようにしましょう。冬は暖かい浴室から外に出ると急激に冷えてしまうので、脱衣所も暖めておくようにしましょう。なお、患者様によって適切なお湯の温度や入浴時間は異なるため、医師から指示された内容をしっかり守るようにしましょう。
軽い運動の習慣化
ウォーキングやサイクリング、エアロビクス、水泳など、軽い有酸素運動を習慣化することが効果的です。運動メニューは激しいものではなく、1分間の心拍数が100~120ほどになる運動が有効です。1日30以上の運動を、少なくとも週に3~4回以上、できれば毎日行うようにしてください。
食事習慣の改善
カロリーや脂質、塩分の摂取量を管理しましょう。高血圧のみならず、様々な生活習慣の改善・予防にも効果的で、老化予防にも繋がります。
減塩
塩分を摂り過ぎると、塩分を薄めようと細胞内の水分が血管内に引き込まれます。それにより、血液量が増え、高血圧状態となります。特に、日本人は日頃から塩分摂取量が多く、1日の塩分摂取量は平均11~12gほどとなっています。摂取量の目標値は男女異なり、男性は8g、女性は7gまでに抑えることで血圧を適正値に維持することが期待できます。無理をしていると長続きしないので、加工食品をできるだけ控える、ハーブや香辛料を使って味付けを工夫するなど、できることから取り組んでみましょう。
カロリー・脂質
肥満の方は、適正体重までダイエットすることで高血圧や他の生活習慣病の改善が期待できます。肥満・高血圧の方で、脂質異常症(高脂血症)や糖尿病のいずれかを合併している場合、特に脂質・カロリー制限に取り組むことが求められます。揚げ物やマヨネーズ、動物性脂肪などを可能な限り控え、海藻や野菜、キノコなどを意識的に摂取し、バランスの整った食事を3食摂るように心がけてください。 肥満の人が1kg減量すると、約2㎜Hgも血圧が低下するといわれています(個人差はあります)。しかし、急激な減量は体への負担が大きいため、正しい方法で行っていきましょう。
嗜好品と血圧
タバコやお酒などの嗜好品も血圧を上昇させるため、節度を持って摂取してください。
喫煙
喫煙習慣があったとしても高血圧にならない場合もありますが、動脈硬化の進行を招き、様々な心、脳疾患のリスクを高めてしまいます。また、喫煙によって高血圧になると、心筋梗塞や脳卒中を発症する可能性を高めます。こうした疾患のみならず、呼吸器疾患の予防にもなるので、節煙・禁煙に取り組みましょう。
飲酒
飲酒が適量であれば問題になることはほぼないですが、大量のお酒を飲むことが多いと、血圧を上昇させてしまいます。また、高尿酸血症(痛風)や肝臓障害、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病を引き起こす恐れもあります。
薬物療法
お薬を使わずに治療を続けていても効果が見られない場合、薬物療法を併用します。降圧剤は様々なものがあるので、患者様の状態や他疾患の有無などから適切なお薬を判断して処方します。また、2種類以上の降圧剤を併用することもあります。 投薬後血圧が下がったからといって、患者様の判断で減薬・休薬してしまうと再度血圧が上昇する可能性があるため、医師から指示された期間内は、決まった時間に服薬を続けましょう。休薬・減薬は医師に相談した上で行うようにしてください。