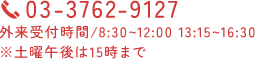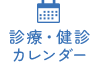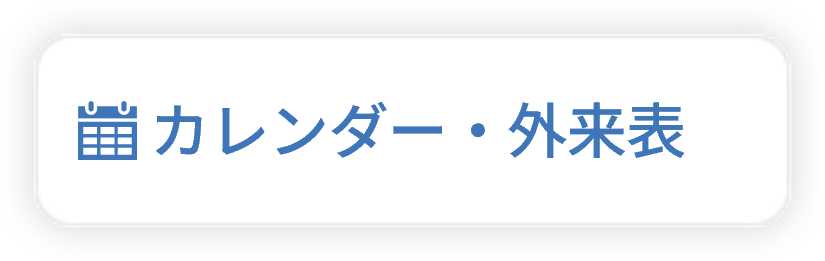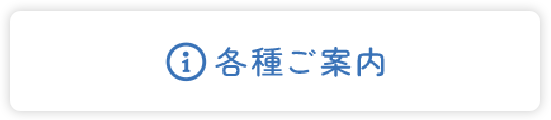すり傷と切り傷
 怪我による傷は、転んだときのように皮膚の表面が擦れてできるすり傷と、ガラスやナイフなど鋭利なもので切られてできる切り傷に分類されます。
怪我による傷は、転んだときのように皮膚の表面が擦れてできるすり傷と、ガラスやナイフなど鋭利なもので切られてできる切り傷に分類されます。
すり傷は皮膚の表面が擦れて傷ついた状態で、基本的に縫合することができません。ですから特に通院の必要はありませんが、砂などの異物が洗浄しても取れない場合は病院を受診する必要があります。
一方、切り傷は傷が小さくても深く切れていることがあります。皮膚が深く切れて肉が見えているような場合や出血が止まらない場合は、病院での縫合が必要です。そのような場合、傷ついてから時間が経つほど感染が起こりやすくなると考えられます。特に顔のように目につきやすい場所の傷を負った場合、早急に受診するようにしてください。
早めに病院を受診すべき傷
- 砂やガラスなど異物が
混入している可能性のある場合 - 傷口が深く肉が分離して、
縫合が必要だと思われる場合 - 出血が止まらない場合
- 感染の可能性がある場合
(熱感がある、腫れている、
膿が出ている、傷が赤い) - 錆びた刃物など汚いもので
傷を受けた場合 - 泥だらけの場所など、
汚い場所で怪我をした場合 - 傷が7〜10日経っても
治らない場合
など
傷が深くまで及んでいる場合
深くまで傷が及んでいる場合、または傷の中で肉が離れていて縫合する必要がある場合は、皮膚科、形成外科、外科で診てもらいましょう。
縫合することで、傷口の治癒が早くなり、傷跡が残らずきれいに治ることが期待されます。特に、鋭利な刃物でできた切り傷は、受傷から6時間以内に傷を洗浄して縫合すれば、感染の心配がなく、傷跡を残さずきれいに治せる確率が高いです。さらに切り傷が深く、神経、腱、関節、内臓まで傷ついている可能性がある場合は、画像診断設備がある病院を受診することをご検討ください。
傷口が深くても適切な処置を受ければ、合併症を起こさずに早期に治癒できると考えられます。
傷口に異物が混入していると思われる場合
切り傷にガラスや金属片などの異物が混入している場合、全ての破片を目視で確認するのが難しいので、医療機関で処置してもらうのが良いでしょう。
医療機関では、拡大鏡を使用して傷口をよく観察し、混入している異物を丁寧に除去する処置が行われます。異物が傷口にあると、傷口が感染するリスクが高まり、その他にも、治癒が遅くなったり、傷跡が残ったりする可能性も高くなります。異物が混入していると思われる場合、早急に医療機関で診てもらいましょう。
感染がある場合
切り傷が細菌感染している場合、速やかに医療機関を受診しましょう。感染の兆候としては、激しい痛み、熱感、腫れ、熱感、膿などがあります。
なお、土や泥などで汚れた環境で怪我をした場合、感染のリスクが高まりますので、怪我の状況も感染しているかどうかの判断基準になります。傷が感染している場合、基本的には抗生物質の内服や外用を行います。感染が悪化した場合、深刻な合併症に繋がるケースもあるため、感染している可能性があれば直ちに医療機関を受診しましょう。
破傷風(はしょうふう)
破傷風は、破傷風菌が原因となる感染症です。破傷風菌は「嫌気性菌」と呼ばれる菌の一種で、酸素がある場所では増殖できず、固い殻(芽胞:がほう)で覆われた状態で、土壌などに存在します。傷口から体内に侵入して、酸素のない場所で発芽し、増殖して毒素を作ります。この毒素が中枢神経にダメージを与えることで、神経の働きを抑制し、過活動状態にします。それにより、筋肉のこわばりや痙攣など様々な症状を示します。
傷が治りにくい場合
切り傷は、基本的には、怪我をした時に適切に手当てをすれば1〜2週間で治ります。
しかし、1週間経過しても治る気配もない場合は、異物の残存、血行不良、感染など何らかの問題があると疑われます。そのため自己判断は控え、傷が治りにくい場合は早めに医療機関で診てもらいましょう。
主な治療対象
消化器の疾患
鼠経ヘルニア
「鼠径部」とは脚の付け根の部分を指し、「ヘルニア」とは体の組織が本来の位置からはみ出す状態を指します。「鼠径ヘルニア」とは、腹膜や腸の一部が、鼠径部の筋膜の弱化により筋肉の隙間から皮膚下に突出する病気です。
一般的には「脱腸」とも呼ばれます。
腹壁瘢痕ヘルニア
腹壁瘢痕ヘルニアは、手術後の傷が完全に治癒せず、お腹に力を入れると傷の部分が盛り上がり、痛みや違和感が生じる状態です。手術後の皮膚は治ったように見えても、筋膜が癒着しておらず、内臓が皮膚の下に突出してしまいます。
開腹手術後の約10%で発生し、腹腔鏡手術後にも見られます。治療には手術が必要で、日本では年間約10,000件の手術が行われています。放置するとヘルニアが進行し、腰痛や便秘、排尿障害、呼吸不全が悪化することがあります。また、腸が脱出したまま戻らない「嵌頓」が発生し、緊急手術が必要になる場合もあります。
胆石症
胆石症は、胆嚢や胆管に結石ができることによって引き起こされる病気です。
肝臓で生成された胆汁は胆嚢に蓄えられ、胆管を通って十二指腸に放出されますが、その過程で胆汁の成分が固まって石を形成します。ほとんどの結石は胆嚢内にできるため「胆嚢内結石」と呼ばれ、まれに胆管内に形成されるものは「肝内胆管結石」や「総胆管結石」と呼ばれます。
胆のう炎
胆のう炎は急性と慢性の2種類に分けられます。
急性胆のう炎は、胆石によって胆のう管が閉塞し、胆のうの粘膜に炎症が生じる病気で、細菌感染が加わると重症化する危険があります。一方、慢性胆のう炎は、繰り返される炎症によって胆のうの壁が厚くなり、胆のう自体が収縮する状態です。
便潜血
便潜血検査は消化管、特に大腸の出血の有無を調べる検査で、健康診断や検診で実施されています。
通常、検査は2回行われます。患者様からは「1回の陽性と診断されたのですが、再検査は必要ですか?」や「再検査の結果が陰性なら大丈夫ですか?」というご質問をよくいただきますが、便潜血検査で1回でも陽性が出た場合は、追加の検査が必要です。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、大腸にできる「いぼ」のような隆起性の病変で、大きさや形状は様々です。
ポリープには非腫瘍性と腫瘍性の2種類があります。非腫瘍性には炎症性や過形成性が含まれ、腫瘍性には腺腫や大腸がんが含まれます。腫瘍性ポリープには隆起性のものに加え、陥没型の腺腫やがんもあります。
胃ろう
口からの食事が困難な方や、むせ込みや肺炎のリスクが高い方に対して、胃に直接栄養を供給する方法が用いられます。これは、腹部に開けた穴からチューブを通して、胃に食事を流し込む手法です。このチューブを「胃ろうカテーテル」と呼び、内視鏡を用いて胃に穴を開ける処置は「PEG(ペグ)」といいます。
胃がん
胃がんは、胃の内側にある粘膜から発生し、そこから次第に粘膜下層、固有筋層、漿膜へと広がります。がんが粘膜または粘膜下層にとどまっている場合を「早期胃がん」と呼び、筋層を超えて広がったものを「進行胃がん」といいます。
大腸がん
大腸がんは、大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんで、便が長時間留まるS状結腸や直腸にできやすいとされています。大腸がんの罹患率は増加傾向にあり、がんによる死亡数では胃がんを抜いて第2位となっています。
肝がん(肝臓がん)
肝臓はお腹の右上に位置し、主に右肋骨に覆われています。成人の肝臓は約1kgで、身体の中で最も大きな臓器です。
肝臓がんは、肝臓から発生する「発性肝がん」と、他の臓器から肝臓に転移する「転移性肝がん」に分類されます。転移性肝がんが最も多く、原発性肝がんには肝細胞がんと肝内胆管がんがあり、肝細胞がんが約95%を占めます。
膵がん(膵臓がん)
「膵がん」とは膵臓に発生する悪性腫瘍で、正式には「浸潤性膵管がん」と呼ばれます。
これは膵液の通り道である膵管から発生し、膵臓内の腫瘍の約90%を占めます。膵がんは特徴的な初期症状がなく、早期発見が難しいがんです。初期には腹部違和感や食欲不振、体重減少などが見られることがありますが、これらは他の病気でも見られる一般的な症状です。
他の悪性腫瘍について
がんの発生部位によって、痛みが現れるタイミングは異なります。多くのがんでは初期には痛みが感じられませんが、脳や食道、頭頸部のがんでは早期に痛みが出ることがあります。
がんが進行するにつれて、出血が大量になり、生命に危険を及ぼすこともあります。また、がんの進行に伴い、一般的には身体の疲労や体重減少が見られ、貧血が進行すると少しの動作でも息切れや疲労感が強くなることがあります。
血管外科疾患
下肢静脈瘤
下肢静脈瘤は、足の表在静脈が異常に拡張し、こぶ状になる病気です。
これは血液が正常に心臓へ戻らず、静脈内に滞留することで起こります。症状は、足のだるさや重さ、むくみ、夜間のこむら返りなどがあり、放置すると皮膚潰瘍や色素沈着などの合併症を引き起こす可能性があります。治療には、生活習慣の改善や弾性ストッキングの着用、硬化療法やレーザー治療、手術による静脈除去があり、症状や患者様の状態に応じて適切な方法が選ばれます。
腹部大動脈瘤
腹部大動脈瘤は、大動脈の壁が弱くなり、こぶ状に膨らむ病気です。
無症状のことが多く、偶然に見つかることも少なくありませんが、こぶが破裂すると激しい腹痛やショック症状を引き起こし、非常に危険です。動脈瘤の大きさが5cm以上になると破裂リスクが高まり、治療が推奨されます。治療は、経皮的ステントグラフト内挿術や開腹手術があり、患者様の全身状態や動脈瘤の位置・形状に応じて選択されます。
皮膚の疾患
粉瘤
粉瘤は、皮膚の下に形成される袋状の腫瘍で、皮脂腺の出口が詰まり、内部に皮脂や角質が溜まることで生じます。
初期には痛みを伴わず、皮膚の下に柔らかいしこりとして触れますが、炎症を起こすと赤みや腫れ、痛み、膿が出ることもあります。粉瘤は自然治癒しないため、炎症が見られる場合は抗生物質を使用し、膿を外に出す切開排膿処置を行います。その後、粉瘤を取り出す手術を行う場合もあります。
アテローム
アテロームは、皮膚の表面に形成される良性の脂肪腫で、表皮内に角質や脂肪が詰まることで発生します。
通常は無症状で、皮膚の下に硬いしこりとして触れますが、感染すると痛みや発熱を伴うことがあります。アテロームは自然に消えることはなく、治療には手術での摘出が必要です。感染を予防するため、早期に処置を行うことが推奨されます。摘出後は再発防止のため、完全に取り除くことが求められます。
脂肪腫
脂肪腫は、皮下に形成される柔らかい脂肪の塊で、通常は良性の腫瘍です。
ゆっくりと成長し、触るとしこりのように柔らかいです。痛みや不快感がないため、そのまま放置されることが多いですが、腫瘍が大きくなり、外見上気になる場合は、外科的に摘出することが可能です。脂肪腫が急激に成長したり、痛みを伴う場合は、まれに悪性腫瘍である可能性があるため、診察を受けることが重要です。
熱傷
熱傷(やけど)は、火や熱い物体、液体、蒸気、化学物質などが皮膚や組織に接触することで引き起こされる損傷です。
軽度のものから重篤なものまで様々で、症状は赤みや痛み、水疱から深い組織損傷に及ぶことがあります。重度の熱傷は感染のリスクが高く、治療が遅れると後遺症が残る可能性があります。治療には、冷却、消毒、湿潤療法などが行われ、場合によっては手術が必要となることもあります。
褥創
褥創(床ずれ)は、寝たきりの方や長期間同じ姿勢でいる方の皮膚や下部組織が圧迫され、血流が阻害されることで生じる壊死性の潰瘍です。特に、尾骨、踵、肘などの骨突出部に発生しやすく、発見が遅れると感染や深い組織への進行を伴い、治癒が困難になります。
予防には、体をこまめに動かし、圧力を分散させるマットレスなどの使用が推奨されます。治療は、創傷ケア、外科的デブリードマン、場合によっては再建手術が必要となることもあります。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)
蜂窩織炎は、細菌が皮膚の深層や皮下組織に感染することで生じる炎症性疾患です。
皮膚が赤く腫れ、熱感や圧痛を伴い、進行すると発熱やリンパ節の腫れが見られます。特に免疫力が低下している人や糖尿病患者は、感染が広がりやすいため注意が必要です。治療には抗生物質の投与を行い、早期の治療が重要です。感染が進行すると敗血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、皮膚の異常を感じた方は速やかに医療機関を受診しましょう。
蜂巣炎(ほうそうえん)
蜂巣炎は、細菌が皮膚のさらに深い層である蜂巣組織に感染することにより生じる炎症です。
蜂窩織炎よりも深刻で、周囲の組織や臓器に拡大するリスクが高いです。症状としては、激しい痛み、強い腫れ、熱感、発熱、さらには全身状態の悪化が見られることがあります。蜂巣炎は適切な治療を行わないと、敗血症や多臓器不全に進展する可能性があるため、緊急の対応が求められます。
治療では広範囲の抗生物質投与と、場合によっては外科的処置が必要になります。
咬傷(こうしょう)
咬傷は、動物や人間に噛まれた際に生じる傷で、細菌感染のリスクが非常に高いです。
傷口から細菌が侵入し、蜂窩織炎や膿瘍、破傷風などの感染症を引き起こすことがあります。特に、猫や犬の噛み傷は深い組織まで達することが多く、感染が拡大しやすいです。咬傷を受けた場合は、早急に傷口を洗浄し、医療機関を受診することが重要です。治療には、抗生物質の投与や、必要に応じてワクチン接種が行われます。
肛門の疾患
痔核(いぼ痔)
痔核は、肛門の静脈が腫れてできる血管のこぶで、内痔核と外痔核に分類されます。便秘や妊娠、長時間の座位などが原因で、肛門周辺に痛み、かゆみ、出血が生じることがあります。
内痔核は肛門の内部に発生し、排便時の出血が主な症状ですが、進行すると痔核が肛門外に脱出することもあります。外痔核は肛門の外側に発生し、痛みを伴うことが多いです。治療には、生活習慣の改善、薬物療法、手術療法などがあり、症状の程度に応じて選択されます。
痔瘻(痔ろう)
痔瘻は、肛門周囲の感染によって膿が貯留し、その排出経路としてトンネル状の病変(瘻孔)が形成される疾患です。
主な症状には、肛門周囲の痛み、腫れ、膿の排出が含まれます。自然に治ることはほとんどなく、外科的手術で瘻孔を切開して清潔に保ち、完全に除去することが治療の基本です。治療後は適切なケアが重要で、再発を防ぐために肛門周囲の清潔を保つことや、排便習慣の改善が推奨されます。早期診断と適切な治療が予後に大きく影響します。
肛門脱
肛門脱は、肛門内の直腸粘膜が肛門外に脱出してしまう状態で、排便時に気づくことが多いです。
原因としては、高齢化による筋力低下や便秘、腹圧の増加などが挙げられます。軽度の場合は自然に戻ることもありますが、重度の場合は自力で戻せなくなることがあり、手術が必要となります。治療には、生活習慣の改善や骨盤底筋訓練が行われ、手術では肛門周囲の筋肉を強化し、直腸を固定する方法が取られます。再発防止のため、術後のリハビリテーションが重要です。
直腸脱
直腸脱は、直腸全体が肛門を通じて外に出てしまう状態で、高齢者や長期間の便秘に悩む人に多く見られます。
直腸脱は、軽度では排便時のみ脱出し、自然に戻りますが、進行すると常に脱出した状態が続き、日常生活に支障をきたします。治療には、まず便秘の改善を図り、保存療法として骨盤底筋トレーニングや、重症例では手術が必要です。手術では、直腸を正しい位置に戻し、腹腔鏡下で固定する方法が一般的です。
内分泌の疾患
甲状腺腫瘍
甲状腺腫瘍は、甲状腺に発生する腫瘍で、良性と悪性のものがあります。
良性腫瘍である「甲状腺腺腫」は他の臓器への影響が少ないため、治療の必要はありません。ただ、悪性腫瘍である「甲状腺癌」は治療が必要です。甲状腺腫瘍は、触診や超音波検査で発見されることが多く、場合によっては細胞診やCT検査が行われます。症状としては、首のしこりや圧迫感、声のかすれが見られることがありますが、無症状のことも少なくありません。
治療には、腫瘍の大きさや種類に応じて、経過観察、手術、放射線療法、内分泌療法が選択されます。