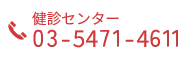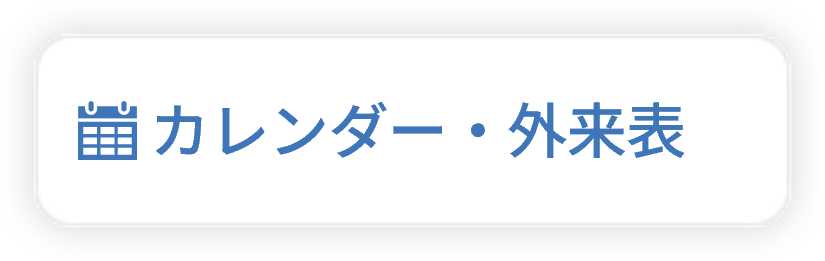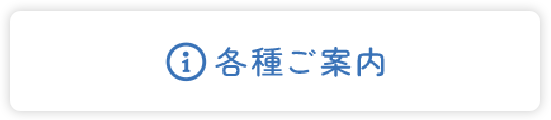いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
疾患一覧
①新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
咽頭痛、鼻水・鼻づまり、咳などの上気道症状に加え、倦怠感、発熱、頭痛、筋肉痛などの症状がみられます。
症状のみから両者を区別することは困難です。
②気管支喘息
アレルギー反応により炎症が起こり、空気の通り道である気道が狭窄する疾患です。
咳、息切れ、喘鳴(ぜんめい:ゼーゼー、ヒューヒューなどの音がすること)などの症状が繰り返し起こります。夜間や早朝に症状が出やすく、運動やストレスなどでも惹起されます。
③咳喘息
咳が3週間以上続くが、痰はあまり絡まない場合、咳喘息の疑いがあります(厳密には8週間以上続く場合に診断されます)。
風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などに続いて発症することが多く、アレルギーの素因を持っている人が発症しやすい病気です。
④気管支炎
ウイルスや細菌などにより、気管や気管支に炎症が起こる病気です。風邪と同様の症状がみられます。
⑤肺炎
主な症状には、発熱、咳、痰の増加、胸痛、呼吸困難などがあります。
特に高齢者や免疫力が低下している人は重症化しやすく、注意が必要です。
⑥マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ・ニューモニエと呼ばれる病原体が原因の肺炎です。 咳や発熱、倦怠感などの症状がみられます。
発熱や倦怠感が治まった後、咳が長引くことがあります。
⑦間質性肺炎
肺胞の壁である間質に炎症が発生する疾患です。
主な症状としては、咳や日常的な動きに伴う呼吸困難が挙げられます。
⑧慢性閉塞性肺疾患(COPD)
喫煙が主な原因となります。長年にわたる喫煙習慣により、肺全体に慢性的な炎症が発生し、少しずつ肺機能が低下していく疾患です。初期は咳や痰などの症状を示し、悪化していくと労作時に呼吸困難に陥るようになり、さらに悪化すると安全時も息苦しさを感じるようになります。重症化した場合、呼吸不全による低酸素血症、肺が破れる自然気胸などに繋がります。
胸部X線検査、CT検査、呼吸機能検査などを行い、診断・重症度を評価します。一度肺が欠損すると元に戻ることはないため、肺機能をこれ以上悪化させないため、そして予防のためにも禁煙が重要です。呼吸不全が悪化した場合は在宅酸素療法を行います。肺炎なども合併しやすいため、こうした疾患の予防も必要です。
⑨非結核性抗酸菌症
非結核性抗酸菌は水や土などどこにでも存在する菌です。咳や痰(血痰)が主な症状で、発熱、倦怠感、寝汗などもみられることがありますが、無症状で健診などの胸部X線検査により発見される場合もあります。
⑩肺結核
肺に結核菌が感染することで生じる疾患です。
主な症状には、咳や痰(血痰)、発熱、体重減少、倦怠感、寝汗などが挙げられます。
⑪慢性誤嚥
誤嚥とは、唾液や食べ物などが誤って気管内に張り込んでしまう状態です。
誤嚥によって肺炎に繋がることがあり、これを誤嚥性肺炎と言います。咳や痰、息苦しさなどの症状を示します。特に、嚥下の機能が落ちている高齢者によく見られます。
⑫胃食道逆流症
胃酸を含む胃の内容物が食道に流れ込むことで、胸やけや呑酸(すっぱいものが上がってくる)、前胸部痛などが起こる疾患です。
また、咳が長引くこともあります。