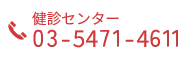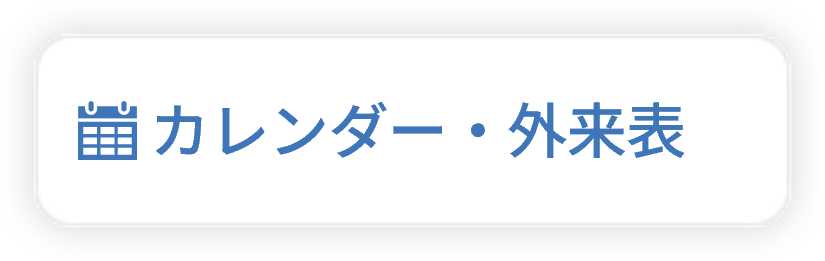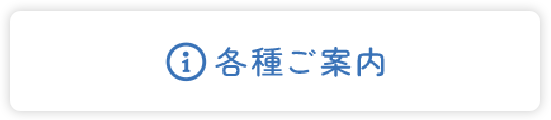いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
脂質異常症について
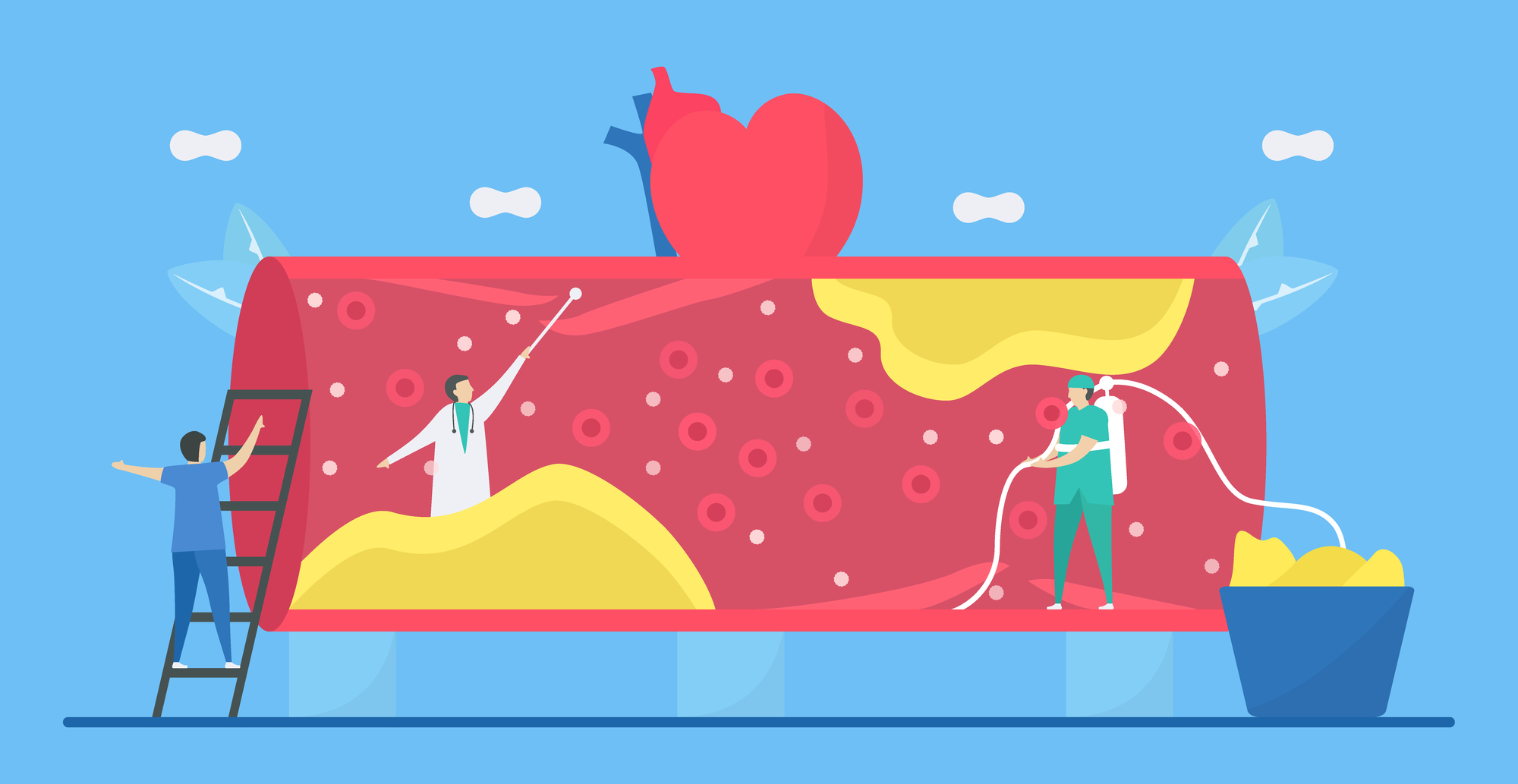 脂質異常症とは、血中の中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールなどの脂質が異常値の状態です。かつては、「高脂血症」と呼ばれていました。
脂質異常症とは、血中の中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールなどの脂質が異常値の状態です。かつては、「高脂血症」と呼ばれていました。
血中の脂質量が異常値になった場合、動脈硬化の進行を招き、脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患に繋がる可能性があります。また、高血圧の方は血管壁に強い圧力がかかっていますが、これに脂質異常症が加わると、より動脈硬化の進行が進みます。また、インスリンの分泌量が低下すると中性脂肪が分解されなくなり、血中に中性脂肪が流れ出し、増加してしまいます。こうした理由から、糖尿病の患者様は脂質異常症の合併リスクが高く、動脈硬化の進行を招いてしまいます。
脂質異常症では、血液がドロドロの状態になります。しかし、自覚症状が乏しく、心筋梗塞などを発症して気づくことも多いです。
深刻な状態にならないように、食事や運動などを習慣的に行い、定期的に健康診断を受けましょう。もし、健康診断で脂質異常症の可能性があると指摘を受けた場合、そのままにせず早めに当院までご相談ください。
脂質異常症の原因
POINT!
脂質異常症の発症には食事が大きく関わっています。
特に、高LDLコレステロール血症や高トリグリセライド血症では、食事が直接的な原因となることが多いので、気を付けましょう。
高LDLコレステロール血症
コレステロールが豊富に含まれる食品(レバー、鶏卵、魚卵)や動物性脂肪が豊富な食品(乳製品、肉類など)を好んで食べることが多いと発症リスクが高まります。また、慢性的なカロリー過多にも気を付けましょう。
高トリグリセライド(中性脂肪)血症
慢性的なカロリー過多が最も多い原因です。暴飲暴食、脂肪分の多い肉類や甘いものなど高カロリーな食品の過剰摂取には気をつけましょう。特に、アルコールの過剰摂取は中性脂肪を増やす要因となるので、ほどほどに抑えましょう。
低HDLコレステロール血症
喫煙や運動不足、肥満などが善玉(HDL)コレステロール値を下げる原因です。食事メニューのバランスに気を付けることに加え、こうした要因にも気を付けましょう。
遺伝と脂質異常症
まれですが、遺伝により脂質異常症になることがあり、これを「家族性高コレステロール血症」と言います。他のタイプに比べ、動脈硬化の進行スピードが早く、食生活の管理に加え、専門科を受診し、適切な治療や指導を受けることが求められます。ご家族や親族などに脂質異常症を発症している方がいらっしゃる場合、なるべく早めに受診しましょう。
脂質異常症の症状
 脂質異常症(特に高LDLコレステロール血症)では、動脈硬化の進行を招き、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患リスクが高まります。高トリグリセライド血症では、急性膵炎のリスクが高まります。家族性高コレステロール血症では皮膚やアキレス腱などに黄色いしこり(黄色腫)ができることもあります。
脂質異常症(特に高LDLコレステロール血症)では、動脈硬化の進行を招き、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患リスクが高まります。高トリグリセライド血症では、急性膵炎のリスクが高まります。家族性高コレステロール血症では皮膚やアキレス腱などに黄色いしこり(黄色腫)ができることもあります。
以下が合併リスクの高い疾患です。
- 狭心症、心筋梗塞
- 脳出血、脳梗塞
- 腎臓障害
- 大動脈瘤、大動脈解離
- 閉塞性動脈硬化症
検査・診断
血液検査により、血中のコレステロール値、中性脂肪値を測ります。
なお、中性脂肪値は食後、時間の経過に伴って高くなるため、正しい数値を測定するためには午前中に食事を摂っていない状態で血液検査を受けることが推奨されます。
診断基準としては以下になります
- LDLコレステロールが140㎎/dl以上:
高LDLコレステロール血症 - 中性脂肪が150㎎/dl以上:
高中性脂肪血症 - HDLコレステロールが40㎎/dl未満:
低HDLコレステロール血症
他の疾患を合併している可能性があれば、その疾患に合った検査を追加で実施します。
TC(総コレステロール)
HDLコレステロール、LDLコレステロール、VLDLコレステロールなどがあり、総コレステロールとはこれらのコレステロール全体を合わせたものです。
LDLコレステロール
LDL(悪玉)コレステロールは、低密度リポタンパク質によって運ばれるコレステロールです。大部分は体内で生成され、一部は食事から摂取されます。細胞膜の形成やホルモン生成に役立ちますが、過剰に増えると血管壁に蓄積し、プラークを形成して動脈硬化を引き起こす原因となります。
HDLコレステロール
HDL(善玉)コレステロールは、高密度リポタンパク質によって運ばれ、体内の余分なコレステロールを肝臓に戻す役割を持ちます。さらに、抗酸化作用や血栓予防、血管内壁の保護、血液凝固の抑制を通じて動脈硬化を防ぐ働きもあります。
TG(トリグリセリド)
血液中の脂肪の一つで、中性脂肪とも呼ばれます。中性脂肪が高いことで動脈硬化が進み、冠動脈疾患などの病気を引き起こしやすくなります。 また、腹部肥満、高血糖、低HDLコレステロール血症、高血圧とともにメタボリックシンドロームの診断基準の項目です。
non-HDLコレステロール
non-HDLコレステロールとは、総コレステロールからHDL(善玉)コレステロールを引いた値を指し、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪の豊富なリポタンパク、脂質異常症により増加するレムナントなどが含まれます。この値が高いほど動脈硬化が進行しやすいです。中性脂肪が400㎎/dL以上の場合、または食後採血の場合、non-HDLコレステロールで評価することが可能です。
脂質異常症の治療
脂質異常症の治療では、はじめに食事療法や運動療法、体重管理、禁煙など生活習慣の改善に取り組みます。
こうした治療でも効果が得られない場合、薬物療法を実施します。
※狭心症や心筋梗塞などの既往歴がある、動脈硬化性疾患を発症しやすい方は、食事療法と運動療法と並行して薬物療法の実施が検討されます。主治医からの指示を守り、治療を進めていきましょう。
(1)食事療法
- コレステロールを豊富に含む食事は
お控えください。 - 食物繊維の多い野菜などを積極的に
摂りましょう。 - 動物性脂肪を減らし、
代わりに植物性脂肪を
積極的に摂取しましょう。 - 糖分の摂取や食べ過ぎに注意し、
摂取カロリーを
コントロールしましょう。 - 節酒しましょう。
- 肉類を減らし、
代わりに魚類を積極的に摂りましょう。
※なお、食事メニューのバランスにも
気を付けてください。
(2)運動療法
無理なく毎日続けられる有酸素運動、例えば1日30分以上早足で歩くなどの運動がお勧めです。
※なお、呼吸器疾患患者、間欠性跛行患者、冠動脈疾患患者、心血管系疾患の発症リスクが高い方や高齢者は注意しましょう。医師に相談のうえ、適切な運動を行ってください。
(3)薬物療法
高脂血症治療薬は、作用機序が異なるお薬が複数あり、グループ分けされています。
医師が患者様の状態、脂質異常症のタイプから適切なお薬を選択します。