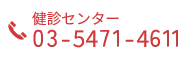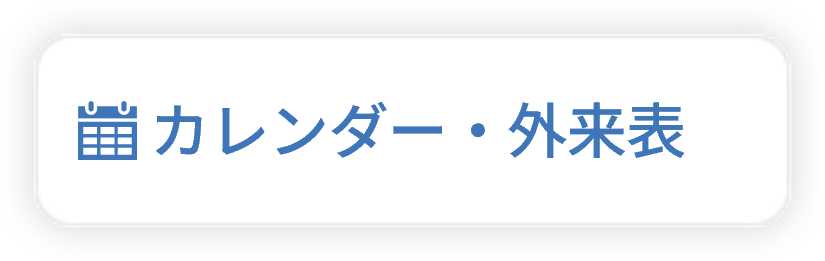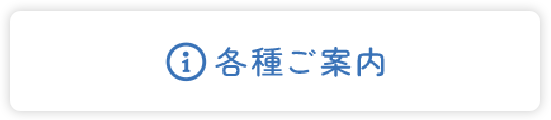いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
HbA1cについて
 HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)とは、血液を流れる赤血球のタンパク質の一種であるヘモグロビンが、どれくらい糖と結びついているかの割合を示す値です。一般的な健康診断における検査項目の一種で、血糖値を適正値にコントロールするための指標です。
HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)とは、血液を流れる赤血球のタンパク質の一種であるヘモグロビンが、どれくらい糖と結びついているかの割合を示す値です。一般的な健康診断における検査項目の一種で、血糖値を適正値にコントロールするための指標です。
ヘモグロビンは酸素を運ぶ役割を担っており、肺で酸素と結合し、全身に酸素を送り届けます。
血糖値とどう違うのか
糖尿病検査では、採血による血糖値の測定も行いますが、これは血中のブドウ糖の濃度を確認して糖尿病を発症していないか、予備軍になっていないかを判断するためです。
血糖値は、直近で行った運動や食事により上下しており、測定した時間帯によって、数値が大きく乖離することがあります。そのため、空腹時血糖値や随時血糖値など、測定のタイミングによって糖尿病の診断となる基準値も異なります。
一方、HbA1c値はヘモグロビンが、どれくらい糖と結びついているかの割合を示す値です。赤血球は120日程度の寿命があり、赤血球が生きている間にヘモグロビンとブドウ糖が結合します。HbA1c値は、食事や運動の影響を受けることがなく、採血から1~2ヶ月間の平均的な血糖値を示し、糖尿病の診断項目として活用されています。
HbA1cの正常値
日本糖尿病学会の糖尿病治療ガイドラインでは、HbA1cの正常値の範囲を「4.6~6.2%」と定義しており、特定保健指導では「5.6%未満」と定義されています。
以下は、日本糖尿病学会の
定義の詳細です。
| 6.0~ 6.4% |
糖尿病を発症している 可能性がゼロではない |
|---|---|
| 6.5%以上 | 糖尿病の可能性が強い |
性別や年齢により正常値は変わりますが、大体5.5%未満が正常値となります。
糖尿病を患っている方は、合併症を防ぐためにも、HbA1c値を7.0%未満までコントロールすることを目標にしましょう。
HbA1c値が高いと疑われる
糖尿病とその概要
POINT!
HbA1c値は直近1~2ヶ月の平均的な血糖値を示す値です。つまり、HbA1c値が高いということは慢性的に血糖値が高い状態にあることを意味します。
HbA1c値が6.5%以上となる場合、糖尿病の可能性が高く、ブドウ糖負荷試験などを追加で検査することが必要です。
糖尿病とは
食事で体内に入った糖質は、消化官を経由する過程で消化・分解されブドウ糖となります。ブドウ糖は血流にのって全身に運ばれ、筋肉や臓器のエネルギーとして消費されます。なかでも、脳はブドウ糖以外をエネルギー源としないため、脳の活動にとって非常に重要な栄養素です。
糖質が体内に取り込まれ、ブドウ糖が血液中に放出されると、膵臓のランゲルハンス島からインスリンと呼ばれるホルモンが分泌されます。インスリンはブドウ糖を筋肉や臓器へ送り込んでエネルギーとして利用したり、肝臓や筋肉でブドウ糖からグリコーゲンが合成されるのを促したりする働きを担い、血糖値を一定に保ちます。
しかし、インスリンの分泌・作用が低下すると、血中のブドウ糖を上手く処理できなくなり、血糖値の上昇を招きます。血糖値が基準値以上となった場合、糖尿病となります。
糖尿病神経障害
以下のような神経障害が起こります。
- 手足の痛み
- 手足の痺れ
- 立ちくらみ
- 感覚麻痺
- 不整脈
- 便秘・下痢
また、血行不良に陥りやすく、潰瘍や壊死に繋がる可能性もあります。
もし、壊死が進んでしまった場合、手術によって患部を切除することが必要になることもあります。
糖尿病網膜症
- 網膜細胞への酸素や栄養の供給不足
- 網膜の血管が障害されることによる出血
- 網膜剥離
上記のような症状が起こり、重症化した場合は失明に繋がる恐れもあります。
糖尿病性腎症
腎臓で血液がろ過され、老廃物は尿となって体外へ排出されています。
糖尿病腎症になると、蛋白が血中から尿中に漏れ出てしまい、血中の蛋白が少なることによって、全身にむくみが現れます。また、腎機能が低下して水分を十分に排出できなくなります。水分が胸に溜まってしまうと呼吸困難になり、酸素投与をしなければならない状態になることもあります。
さらに、腎不全に至ると、腎臓機能を代替するための透析治療が必要となります。糖尿病は、透析治療を導入する疾患として最多となっています。
糖尿病では、上記のような毛細血管の障害によって起こる合併症に加え、大血管の動脈硬化が進行する可能性もあります。
これにより、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な疾患を引き起こしたり、足部が血行不良になることで間歇性跛行(かんけつせいはこう)と なり、休みながら出ないと歩くことができなったりする可能性もあります。
高齢者の糖尿病
POINT!
現在、高齢者人口は増加し続けています。年齢を重ねることで膵臓の機能は低下するため、糖尿病患者の高齢者の比率が高くなってきています。男女別で、糖尿病の発症リスクが高い方の割合は以下のようになっています。
- 男性:50代(約18%)、
60代(12~13%)、
70代以上(18~19%) - 女性:50代(約9~10%)、
60代(15%)、
70代以上(20%)
高齢者糖尿病の特徴
高齢者糖尿病とは、65歳以上で発症する糖尿病のことです。年齢を重ねることで膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞が少なるため、 それに伴ってインスリンの分泌量も低下します。また、内臓脂肪量の増加、筋肉量・質の低下、運動量の低下などにより、インスリン抵抗性が高くなり、エネルギーとしてブドウ糖を利用する量が減るため、糖尿病を発症しやすくなります。若年層の糖尿病と症状や併存疾患、合併症が異なり、身体機能や認知機能、社気・経済事情なども人によって異なるので、血糖を上手くコントロールするのが困難になり ます。
また、年齢を重ねることで身体の変化に対応する力も減少するため、安全面に注意を払いながら血糖をコントロールすることが求められ ます。