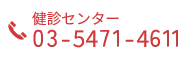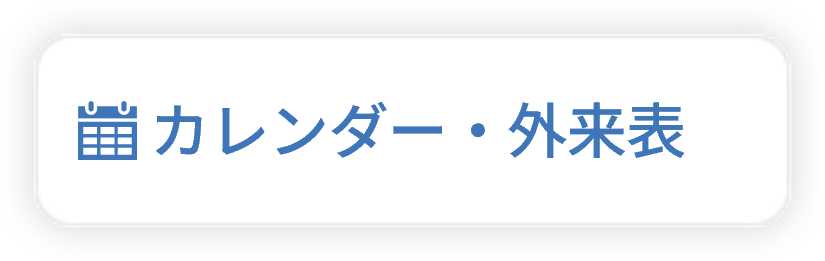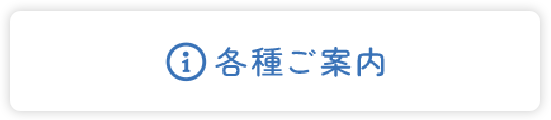いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
糖尿病とは
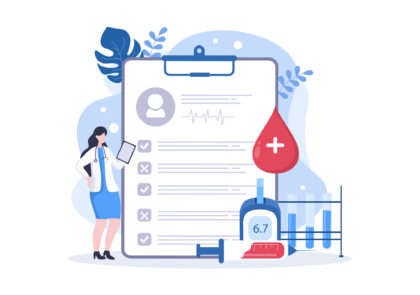 糖尿病は、膵臓から分泌されるホルモン(インスリン)の量が減少、または作用が低下することが原因で、血中のブドウ糖濃度が高い高血糖状態が慢性的に続く病気です。糖尿病は、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病、妊娠糖尿病の4種類に分けられます。日本人に特に多いのは2型糖尿病で、全体の95%以上に上り、世間で言う糖尿病はこのタイプに当てはまります。
糖尿病は、膵臓から分泌されるホルモン(インスリン)の量が減少、または作用が低下することが原因で、血中のブドウ糖濃度が高い高血糖状態が慢性的に続く病気です。糖尿病は、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病、妊娠糖尿病の4種類に分けられます。日本人に特に多いのは2型糖尿病で、全体の95%以上に上り、世間で言う糖尿病はこのタイプに当てはまります。
2型糖尿病は、遺伝や生活習慣が原因です。 糖尿病は高血圧と同様に、「サイレントキラー」と表現され、初期は自覚症状が乏しく、倦怠感やのどの渇き、頻尿など軽い症状となります。悪化していくと、我慢できないほどののどの渇き、体重減少が起こり、病院を受診してようやく糖尿病と分かることがあります。なお、糖尿病は重症化すると腎不全を引き起こし、透析が必要になることがあり、透析治療を導入する疾患として最多となっています。
他にも、下肢の切断や失明に至る恐れもあり、日常生活に重大な影響を及ぼします。脳梗塞、心筋梗塞などの動脈硬化性疾患も糖尿病に合併しやすい疾患です。
2019年の「国民健康・栄養調査」のデータでは、糖尿病予備軍の割合は、男性では19.7%(5人に1人)、女性では10.8%(10人に1人)となっており、多くの方が発症する可能性のある疾患です。
糖尿病の検査について
問診
発症初期、または血糖値があまり高くない場合は、はっきりとした症状が現れません。
そのため、問診、採尿や採血などを実施して、正確に病状を確認する必要があります。問診では、下記の内容を丁寧にお伺いします。
- 現在の体調
- 自覚症状の有無
- 自覚症状がある場合はその内容
- 既往歴の有無
- ストレスの有無
- 日頃の食事や運動
- 飲酒・喫煙習慣の有無
- 最近、体重の増減があったか
- ご家族に糖尿病を患っている方がいるか
など
尿糖検査
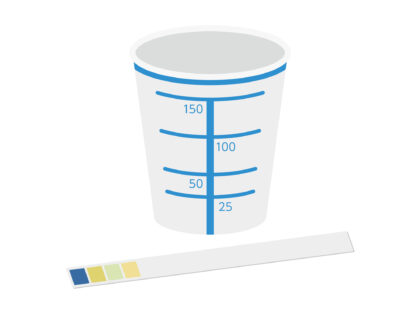 尿糖検査では、尿に含まれるブドウ糖の量を調べます。尿に糖が出ると糖尿病を心配する方もいらっしゃいますが、高血糖状態が慢性的に続いているかどうかが確定診断を下す重要なポイントになります。血糖値が正常な場合でも、尿糖検査では陽性と出ることもあります。
尿糖検査では、尿に含まれるブドウ糖の量を調べます。尿に糖が出ると糖尿病を心配する方もいらっしゃいますが、高血糖状態が慢性的に続いているかどうかが確定診断を下す重要なポイントになります。血糖値が正常な場合でも、尿糖検査では陽性と出ることもあります。
そのため、尿糖検査で陽性となった場合、血糖測定検査やブドウ糖負荷試験も受けて頂き、最終的な診断を下します。
血糖測定検査
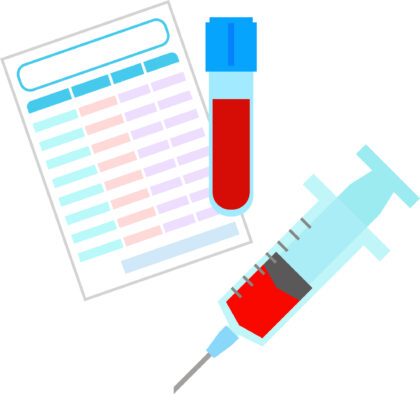 血糖測定検査は、血中のブドウ糖の量を調べる検査です。
血糖測定検査は、血中のブドウ糖の量を調べる検査です。
血糖値を測定するタイミングは目的によって異なり、空腹時血糖値、随時血糖値、ブドウ糖負荷試験の血糖値の3つがあります。
- 空腹時血糖値
その名の通り空腹時に測る血糖値です。10時間以上空腹な状態を維持して頂き、基本的には検査当日の朝は食事を控えた状態で検査を実施します。空腹時血糖値が126mg/dLの場合は糖尿病と診断されます。 - 随時血糖値
食事時間とは無関係に測る血糖値です。随時血糖値が200mg/dL以上の場合は糖尿病と診断されます。 - ブドウ糖負荷試験
ブドウ糖液を少量飲んだ後、いくつかのタイミングで血糖値を測定し、血糖値の変化、インスリンの分泌量やインスリン抵抗性も確認します。
※糖尿病は、上記3つの検査のうち、どれか1つでも基準値を超えている状態を指します。同じ検査を別日に行った際も、異常値が出た場合は糖尿病の確定診断が下ります。また、上記いずれかの検査で糖尿病が疑われる数値が出ており、HbA1c(ヘモグロビンがブドウ糖と結びついている割合を示す値)が6.5%以上と出た場合も糖尿病の確定診断が下ります。
HbA1cとは
HbA1cとは、赤血球内のタンパク質の1つであるヘモグロビンが、どれくらいブドウ糖と結びついているかの割合を示す値です。
赤血球は120日程度の寿命があり、一度ブドウ糖と結合したヘモグロビンは赤血球が生きている間は分離することがありません。
そのため、食事や運動の影響を受けることがなく、採血から1~2ヶ月間の平均的な血糖値を測定することが可能です。
血糖値との違い
血糖値は1日の中で、運動や食事などの影響を受けて変動する特徴があります。
また、糖尿病の進行に伴って変動幅も大きくなります。そのため、検査を受けるタイミングによって血糖値は変動するので、早朝に空腹の状態で血糖値を測定すると最小値を示すことが多く、たとえ血糖値が上がる時間帯があったとしても糖尿病の発見に至らないこともしばしばあります。
一方、HbA1cは食事や運動に影響されず、1~2月間の平均的な血糖値を測定できるため、初期の糖尿病の発見に役立ちます。
HbA1cの正常値
HbA1cの正常値は、日本糖尿病学会では以下のように4.6~6.2%と定義しています。
なお、特定保健指導の正常値は5.6%未満です。
| 4.6〜 6.2% |
正常値 |
|---|---|
| 6.0〜 6.4% |
糖尿病の可能性が ゼロではない |
| 6.5%以上 | 糖尿病の可能性が高い |
糖尿病を患っている方は、合併症を防ぐためにも、HbA1c値を7.0%未満までコントロールすることを目標にしましょう。ただし、低血糖にも気を付ける必要があり、年齢や服用中のお薬、認知機能の程度次第で目標値が変わることもあります。
糖尿病の診断基準
- Ⅰ.早朝空腹時血糖値126mg/dL以上
Ⅱ.75gブドウ糖負荷試験(OGTT)
2時間値200mg/dL以上
Ⅲ.随時血糖値200mg/dL以上
Ⅳ.HbA1c6.5%以上
のうちⅠ~ⅢのいずれかとⅣが確認されれば、糖尿病と診断する。
※ストレスのない状態での高血糖の確認が必要 - Ⅰ~Ⅳのいずれかひとつだけを認めた場合は「糖尿病型」と診断する。別の日に再検査を行い、再び「糖尿病型」が確認されれば糖尿病と診断する。ただし、HbA1cのみの反復検査で糖尿病と診断することは不可とする。
- 血糖値が「糖尿病型」(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を示し、かつ次のいずれかの条件が満たされた場合は糖尿病と診断する。
・糖尿病の典型的症状
(口渇、多飲、多尿、体重減少)の存在
・確実な糖尿病網膜症の存在
OGTT検査(経口糖負荷試験)
糖尿病の前段階(境界型)
糖尿病の診断では、基本的に血液検査を行い、空腹時の血糖値やHbA1cを確認します。
しかし、境界型(糖尿病予備軍)の段階では空腹時は血糖値が正常範囲内でも、食後は血糖値が高値を示すことがあります。
また、糖尿病の基準値には届いてないものの、空腹時血糖が高値を示すこともあります。この時期には動脈硬化が進行し始めており、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な疾患のリスクが高まっていると考えられています。
OGTT検査
(経口糖負荷試験)とは
OGTT検査(経口糖負荷試験)とは、境界型の段階も判定可能な検査です。
下記の項目に1つでも当てはまる方に推奨されます。
- HbA1c 5.2%以上となっている方
- 糖尿病を発症している血縁関係がいる方
- 高血圧・高脂血症の方
- 尿糖検査で陽性と出た方
- 特定健診(メタボ健診)で異常を
指摘された方
検査方法
- 前日の夜22時から約10~16時間は絶食して頂きます。なお、水であれば飲んで頂いて問題ありません。
- 血液検査を行い、
血糖値やインスリン値を測定します。 - ブドウ糖75gを溶かした水を
飲んで頂きます。 - ブドウ糖を溶かした水を飲んだ後、30分刻みで合計4回血液検査を行い、血糖値やインスリン値を測定します。
結果判定
空腹時血糖値および75g糖負荷試験(OGTT)2時間値の判定基準
| 正常域 | 糖尿病域 | |
| 空腹時血糖値 | <110 | ≧126 |
| 75g OGTT 2時間値 | <140 | ≧200 |
| 75g OGTTの判定 | 両者を満たすものを正常型 | いずれかを満たすものを糖尿病型 |
| 正常型にも糖尿病型にも属さないものを境界型とする | ||
随時血糖値が200mg/dL以上の場合も糖尿病型と判断されます。
正常型の場合も、1時間値が180mg/dL以上であれば、180mg/dL未満の方よりも糖尿病に移行するリスクが高いため、経過観察など境界型に則った対応が必要になるケースもあります。
インスリンについて

インスリンは、膵臓のランゲルハンス島という組織内部にあるβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる作用があります。
血糖値が上がると、インスリンはブドウ糖をエネルギー源としたり、筋肉や肝臓、脂肪組織にブドウ糖を貯えたり、タンパク質の合成を促す働きをします。それにより、血糖値を一定に保ちます。
インスリン治療
 運動療法や食事療法、薬物療法では十分な効果が得られない場合、インスリン注射を実施します。インスリン注射にネガティブな印象をお持ちの方もいますが、早期に実施することで過剰に負担がかかっていた肝臓を休ませることができます。
運動療法や食事療法、薬物療法では十分な効果が得られない場合、インスリン注射を実施します。インスリン注射にネガティブな印象をお持ちの方もいますが、早期に実施することで過剰に負担がかかっていた肝臓を休ませることができます。
肝臓機能が元に戻り、インスリン注射を必要としない状態になっても、血糖値の上昇を抑えられるようになることもあります。合併症を防ぎ、健康的な生活を送るためにもインスリン注射は非常に有用な治療法です。
インスリン注射で使用する針は痛みが少なく、容器も改良が進んでおり、誰でも簡単に行えます。
インスリンの種類
インスリンには複数の種類があり、血糖値が低下するまでの時間によって、持続型(持効型溶解)、中間型、速効型、超速効型に分けられます。
種類によって、効果の発現開始時間は15分から3時間と時間差は 大きく、患者様の病状に適した種類のものが選択されます。
インスリン治療の種類
インスリン療法は、下記の4種類に分けられます。
BOT療法
(Basal Support Oral Therapy)
持続型のインスリンを1日1回注射し、内服薬も併用する治療法です。医師に指示に従って注射回数を守って頂ければ、タイミングはいつでも大丈夫です。
持続型のインスリンを使用するため、ゆっくりと効果が現れ、血糖値が急激に下がることはなく、低血糖になりにくい安全な方法です。
混合型インスリン製剤による治療
超即効型もしくは即効型に、中間型のインスリンを混ぜた薬液を注射します。
混合割合は25~50%程度の範囲で調整し、患者様の病状に応じて割合を決定します。注射回数は1日1~2回となり、経過次第では回数を減らすこともあります。
追加インスリン療法(3回法)
毎食前に、超速効型もしくは即効型のインスリンを注射します。食後は血糖値が上がり、インスリン分泌(追加分泌)が起こるので、この分泌を補う形となります。
なお、注射後、食事を摂るタイミングが遅れたり、食事を摂らなかったりした場合、低血糖になる可能性があります。低血糖になった場合、少しでも食事を摂るか、もしくはブドウ糖を補給する必要があります。
基礎―追加インスリン療法
空腹時にインスリンが一定分泌されることを基礎分泌と言います。
基礎分泌を補う形で持続型インスリンを1日1回、食後に起こる追加分泌を補う形で速攻型インスリンを1日1〜3回注射し、血糖管理を行います。