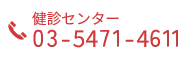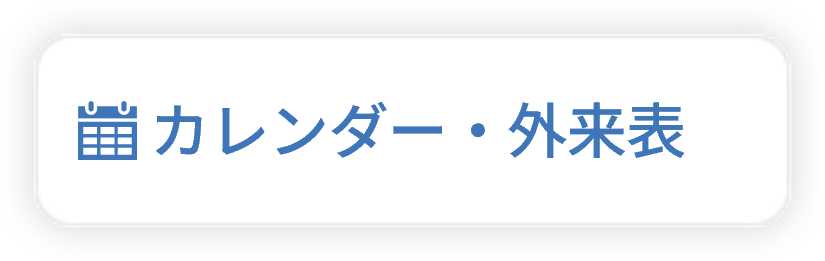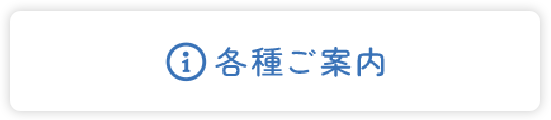いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。
再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。
糖尿病について
 糖尿病は、膵臓で分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンの作用が低下、もしくは分泌量が低下することで、血中のブドウ糖濃度が高くなり、「高血糖状態」が慢性的に続く病気です。
糖尿病は、膵臓で分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンの作用が低下、もしくは分泌量が低下することで、血中のブドウ糖濃度が高くなり、「高血糖状態」が慢性的に続く病気です。
糖尿病は、「1型糖尿病」「2型糖尿病」「その他の糖尿病」「妊娠糖尿病」の4種類に分けられます。日本人に特に多いのは2型糖尿病で、全体の95%以上に上り、世間で言う糖尿病はこのタイプに当てはまります。2型糖尿病は、遺伝や生活習慣が原因です。
糖尿病は高血圧と同様に、「サイレントキラー」と表現され、初期は自覚症状が乏しく、のどの渇きや倦怠感、頻尿など軽い症状が起こります。悪化していくと、我慢できないほどののどの渇き、体重減少が起こり、気になって受診することでようやく糖尿病と判明することがあります。なお、糖尿病は悪化すると、腎不全に至り、透析が必要になることがあり、透析治療が必要な疾患として最も多いものです。他にも、下肢の切断や失明に至る恐れもあり、日常生活に大きな影響を与え(あたえ)ます。
2019年の「国民健康・栄養調査」のデータでは、糖尿病予備軍の割合は、男性では19.7%(5人に1人)、女性では10.8%(10人に1人)となっており、多くの方が発症する可能性のある疾患です。
糖尿病のタイプ
1型糖尿病
原因は明らかになっていないことが多いですが、突如、自己免疫によりインスリンを分泌する膵臓のB細胞が破壊されることによって起こります。インスリンを分泌することができなくなるため、治療ではインスリン療法を行います。特に小児~青年期によく発症しますが、高齢で発症することも少なくありません。
2型糖尿病
2型糖尿病の原因は、暴飲暴食、肥満、運動不足などの生活習慣の乱れや遺伝的な体質が挙げられます。こうした要因により、インスリンの作用低下や分泌量が低下し、発症に至ります。幼少期に発症することは滅多になく、肥満が増加する青年期以降の発症ケースが多いです。
治療は運動療法と食事療法が基本となります。運動によって肥満解消、筋力を増加させてインスリンの効き目を改善し、食事での糖質摂取量を抑えることで血糖値を安定化させます。こうした治療法で十分な効果が得られない場合、経口糖尿病薬やインスリン療法を併用して治療を行います。
糖尿病の診断基準
POINT!
糖尿病は高血糖が続いている状態のため、診断には血糖値とHbA1c(1~2ヶ月の血糖値の平均)の数値を確認します。
健康な方は、食前・食後を含め血糖値が70~140mg/dLの範囲に収まります。
空腹時の血糖値が100~109mg/dL
空腹時の血糖値が100~109mg/dLの場合は「正常高値」とされ、将来的に糖尿病のリスクがある状態です。
空腹時の血糖値が110~125mg/dL
空腹時の血糖値が110~125mg/dLの場合は「境界型」とされ、糖尿病になる前の状態で「糖尿病予備軍」とも呼ばれます。糖負荷試験(75gOGTT)などの検査の受診が推奨されます。
空腹時の血糖値が126mg/dL以上、
もしくは食後の血糖値が
200mg/dL以上
空腹時血糖が126mg/dL以上、あるいは食後血糖が200mg/dL以上の場合、糖尿の可能性が高いです。あわせて測定したHbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病と診断されます。
※血糖値のみでは、1回の検査で診断を確定できません。
自覚症状や網膜症が認められる場合
HbA1cの値に関係なく、糖尿病でよくある「倦怠感」「のどの渇き」「多尿」などの症状がある場合、または糖尿病網膜症が認められる場合、糖尿病の診断となります。
※甲状腺機能亢進症やヘモグロビン異常症など、糖尿病以外の疾患でもHbA1cが高値を示すことがあるので、診断を確定するには血糖検査が不可欠です。
糖尿病の発症リスクが高い人
下記に該当する方は糖尿病を発症
しやすいので気を付けましょう。
- ご飯やパン、芋、麺の摂取量が多い
- 脂っこい食事を摂ることが多い
- ジュースや清涼飲料水などの
甘い飲み物を好む - 自炊よりも外食の回数が多い
- 飲酒習慣がある、飲酒量が多い
- 肥満
- ストレス過多
- 車移動が多く、日頃歩くことが少ない
- 家族の中で糖尿病を
発症している方がいる
糖尿病の初期段階は
症状がほとんどない
POINT!
糖尿病は「サイレントキラー」と表現されており、初期は自覚症状がほとんどなく、病気が進行してからようやくはっきりとした症状が現れます。
症状が現れた段階では、重大な合併症を発症している可能性もあります。
高血糖に伴う症状
- すぐ疲れる
- 食後数時間程度でお腹が減る
- のどが乾きやすい
- 多尿・頻尿
- これまでと同じ量を食べているのに
体重が減ってくる
糖尿病に伴う合併症
- 糖尿病網膜症(目がかすむ、まぶしい)
- 糖尿病腎症
(足がむくむ、血圧が高い、息切れ) - 糖尿病神経症
(手足のしびれや違和感がある)
糖尿病の治療
1型糖尿病の治療
 1型糖尿病では、インスリン注射を用いた治療を生涯にわたって継続する必要があります。
1型糖尿病では、インスリン注射を用いた治療を生涯にわたって継続する必要があります。
現在のところ、インスリン注射以外の治療法は開発されていません。
2型糖尿病の治療
 糖尿病治療で一番大切なことは、患者様自身が糖尿病についてしっかり理解し、悪化を防ぐための食事や運動などの生活習慣の改善にご家族と一緒に取り組んでいくことです。
糖尿病治療で一番大切なことは、患者様自身が糖尿病についてしっかり理解し、悪化を防ぐための食事や運動などの生活習慣の改善にご家族と一緒に取り組んでいくことです。
当院では、患者様が積極的に糖尿病治療に取り組み、その意欲を維持して成果に向けて取り組んでいけるようにサポートします。
患者様1人ひとりに応じた
食事療法と運動療法
2型糖尿病の治療は、運動療法と食事療法が基本になります。ただ、食事内容を管理したり毎日運動したりするのは億劫だと思います。
当院では、各患者様の生活習慣、身体の状態、趣向に応じて、無理のない範囲で続けられるメニューを提案しています。
当院の食事療法
- 血糖コントロールを安定化させられる身体、つまり体脂肪が少なく筋量が多い身体を目指すために、体組成計を用いて脂肪量と筋量を測定します。
- 食事での糖質量が過剰になっていないか、摂取量の目安をアドバイスします。
- 食事を食べる順番も大切で、
野菜→タンパク質・脂質→糖質
の順に食べましょう。 - 間食は控えて頂きます。
- 暴食した場合の対処法などを
アドバイスします。
日々の食事で上手く管理できている部分、できていない部分を患者様と一緒に確認し、改善できる部分をアドバイスします。
当院の運動療法
患者様の運動の好み、運動経験の有無、生活習慣、既往歴などを考慮し、取り組みやすく無理なく続けられるメニューを提案します。 食後に医師が提案したメニューを取り組むことで、食後の血糖値の上昇を抑えられます。